全国で深刻化する空き家問題。2018年の調査では、その数はなんと849万戸に上り、少子高齢化と人口減少が進む日本において、今後も増加の一途を辿ると予測されています。
もしあなたが、親御さんが住む実家を将来相続する予定がある、あるいは既に相続したものの、管理の負担や空き家になる可能性に頭を悩ませているなら、実家の売却は重要な選択肢の一つです。
この記事では、このような疑問や不安を抱えるあなたに向けて、親御さんの生前に実家を売却する場合と、相続後に売却する場合のメリット・デメリットを徹底比較します。税制上の特例や控除を理解することで、売却額が大きく変わる可能性も。使わない実家があるなら、親御さんとじっくり話し合い、最適な売却タイミングを見極めることが重要です。さらに、空き家の維持管理と更地にする選択肢についても詳しく解説します。
空き家になる実家、どうする?「使う」「売る」それぞれの選択と注意点

親御さんが住まなくなった実家は、今後「使う」か「使わない」かの二つの大きな選択肢に分かれます。それぞれの選択肢には、さらにいくつかの活用方法と考慮すべき点があります。
「使う」という選択
実家への思い入れや将来的な可能性を考えると、「使う」という選択肢も魅力的です。具体的な活用方法としては、以下のようなものが考えられます。
維持管理して所有: 思い出の詰まった実家を手放したくない場合に、定期的な維持管理を行いながら所有し続ける。
Uターン・Iターンして居住: 親御さんと離れて暮らしていた家族が、実家に戻って暮らす。リフォームを施し、快適な住まいとして再生させることも可能です。
賃貸として活用: 実家に戻る予定がない場合、リフォームして賃貸物件として活用し、家賃収入を得る。
更地にして土地活用: 建物を解体し、駐車場や資材置き場など、土地として活用する。
もし実家をリフォームして活用することを検討しているなら、以下のサイトで複数のリフォーム会社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。地域の最安値を知ることで、賢くリフォームを進められるでしょう。
こちらのリフォーム会社一括見積もりサイトで、エリアごとの実家リフォームの最安値を出してリフォーム会社を選ぶといいでしょう。
「使わない」という選択
実家を活用する予定がない場合は、「売却」という選択肢が現実的です。特に、親御さんがご高齢になり、老人ホームへの入居を検討している、あるいは既に入居された場合、介護のために同居することになった場合などは、実家が空き家になる可能性が高くなります。
空き家になる実家の売却は、親御さんが元気なうちに話し合い、 売却の意向や希望条件を決めることが重要です。
空き家を放置するリスク
実家を空き家のまま放置することは、様々なリスクを伴います。
固定資産税の負担: 不動産を所有している限り、たとえ住んでいなくても固定資産税は発生し続けます。
近隣トラブルの可能性: 建物の老朽化による倒壊の危険、雑草の繁茂、害虫の発生などは、近隣住民とのトラブルの原因になります。
固定資産税の増額: 特定空家(管理不全な空き家)に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、最大で6倍になる可能性があります。
管理費用の発生: 定期的な清掃やメンテナンスなど、維持管理のための費用がかかります。
これらのリスクを考慮すると、管理が難しい空き家は、放置せずに売却を検討することが賢明な判断と言えるでしょう。
これから実家(空き家)を売却しようと考えている方へ向けて、売却前に知っておくべき情報や、空き家を高く売るためのポイント、注意点を紹介します。詳しく知りたい方は、ぜひ下の記事をご覧ください。
空き家になる実家、「生前」売却と「相続後」売却、どちらが得?
兄弟姉妹がそれぞれ独立し、親御さんが亡くなると実家が無人となり、空き家として放置されるケースが増えています。空き家となった実家を売却して現金化するか、賃貸物件として活用し家賃収入を得るのが一般的な選択肢です。

実家を売却する際、多くの方ができるだけ高値で売りたいと考えるでしょう。
空き家になる実家を売却する場合、親御さんがご存命の「生前」に売却するのか、亡くなられた「相続後」に売却するのかによって、適用できる税金の特例や、所得税・相続税の金額が異なります。
利用できる特例の条件や税金についてしっかりと確認した上で、親御さんの「生前」と「相続後」のどちらのタイミングで売却するのがより有利になるのか検討しましょう。

親御さんのご存命中に実家を売却する

親御さんがお元気なうちに話し合うことで、ご本人の意向を直接確認できます。相続発生後の不要な争いを避け、一定の条件を満たす特例を活用することで、税負担を軽減しながら財産を受け取ることが可能です。ただし、親御さんがご存命の間は、実家の所有権は親御さんにありますので、お子様が独断で売却することはできません。
相続した実家を売却する際には、相続人全員の同意が必要となります。そのため、親御さんがお元気で意思表示ができるうちに売却の手続きを進めることが望ましいでしょう。親御さんが認知症や病気などにより意思表示が困難な状態になると、「売却への意思表示が確認できない」として、売却手続きが非常に難航する可能性があります。
親御さんの「生前」に実家を売却するメリット
- お子様が実家に戻る予定がなく、将来的に空き家になる不安や管理のリスクを解消できます。
- 実家を残しても相続が難しいと判断される場合、生前に売却して現金化できます。
- 売却によって得た資金を、親御さんの高齢者施設への入居費用などに充てられます。
- 売却により、高齢者施設入居後の実家の維持管理の負担がなくなります。
- 相続後、お子様が実家の維持管理や売却の手続きに苦労する事態を避けられます。
- 売却した資金を、親御さんの老後の生活費に活用できます。
- 相続時の親族間のトラブルを抑制できます。
- お子様が主体となって売却活動を進めやすくなります。
- 遺産分割協議において、売却代金を公平に分割する換価分割がスムーズに行えます。
実家の売却価格を査定して、分割できる遺産を把握しましょう。売却後の建物や設備へのサポートがありますので安心して売却できます。1分で売却価格をシミュレーションできますのでご活用下さい。
「居住用財産の3,000万円特別控除」を活用!自宅売却でお得に

ご自身やご家族が住んでいた家屋(居住用財産)を売却する際には、「居住用財産の3,000万円特別控除」という税制上の優遇措置が利用できます。これは、不動産の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
具体的には、現在住んでいる自宅、あるいは過去に住んでいた自宅とその敷地などを売却した場合、一定の適用要件を満たせば、売却益が3,000万円以上であれば3,000万円が控除され、売却益が3,000万円以下の場合はその金額が全額控除されます。
譲渡所得とは、一般的に、土地や建物などの資産を売却することによって得られる所得のことです。譲渡所得の金額は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得の金額=収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額
収入金額: 不動産の売却代金
取得費: 不動産の購入代金や建築費用、改良費など
譲渡費用: 不動産売却時に支払った仲介手数料、印紙税などの費用。空き家売却のために建物を解体して土地のみを引き渡す場合の解体費用も譲渡費用に含まれます。
特別控除額: 居住用財産の3,000万円特別控除など
3,000万円特別控除を受けるための主な適用要件
- 売却する物件がご自身の居住用財産であること(別荘などは対象外)。
- 住んでいた自宅であれば、引っ越し後3年後の年末までに売却すること。
- 売却先が親族(配偶者、直系血族、生計を一にする親族)以外であること。
- 他の譲渡所得に関する特例の適用を受けていないこと。
- 住宅ローン控除との重複適用はできません。
- 災害により家屋が滅失した場合、住まなくなった日から3年を経過する日の年末までに売却すること。
- 自宅を解体して土地のみを売却する場合は、家屋を取り壊した日から1年以内に売却すること。また、解体後に賃貸するなど、特定の要件を満たさない場合は控除を受けられません。
空き家の実家を売却する場合の注意点
親御さんと離れて暮らしているお子様が、空き家になった実家を相続後に売却する場合、その実家はお子様の居住用財産とはならないため、原則としてこの3,000万円特別控除は適用できません。ただし、実家で親御さんと同居していたお子様が相続し、その後もその家を自宅として使用している場合は、3,000万円特別控除の適用が可能です。

このように、「居住用財産の3,000万円特別控除」は、ご自身が住んでいた家を売却する際に大きな節税効果を発揮する可能性があります。適用要件をしっかりと確認し、有利に売却を進めましょう。
「10年超所有軽減税率の特例」で譲渡所得税を軽減!

一定の要件を満たすと、居住用財産(自宅)を売却した際の譲渡所得税率が軽減される「10年超所有軽減税率の特例」が適用できます。この特例の適用を受けるためには、売却した年の1月1日時点で、売却する自宅(建物と土地)の所有期間が10年を超えている必要があります。
譲渡所得は、所有期間に応じて「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の2種類に区分され、税率が異なります。
- 長期譲渡所得: 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超の場合に該当し、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
- 短期譲渡所得: 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合に該当し、税率は39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)となります。
「10年超所有軽減税率の特例」は、この長期譲渡所得の税率をさらに軽減するものです。
特例の主な適用要件
- 日本国内にあるご自身の居住用財産(自宅とその敷地)の売却であること。別荘や投資用物件など、居住を目的としない不動産は対象外です。
- 売却先が親族(配偶者、直系血族、生計を一にする親族)以外であること。
- 売却した年の1月1日時点で、売却する建物と土地の所有期間がいずれも10年を超えていること。
- 災害により家屋が滅失した場合、住まなくなった日から3年を経過する日の年末までに売却すること。
- 更地で売却する場合、譲渡契約締結日まで賃貸事業などの用途に使用していないこと。
この「10年超所有軽減税率の特例」は、前述の「居住用財産の3,000万円特別控除」と併用が可能です。両方の特例を適用することで、譲渡所得税を大幅に軽減できる可能性があります。
ただし、「住宅ローン控除」や「特定の居住用財産の買換え特例」との併用はできませんのでご注意ください。

所有期間が10年を超える自宅を売却する際には、この軽減税率の特例を忘れずに確認し、賢く節税を行いましょう。
実家の名義を生前変更すると贈与税はいくらかかる?相続との比較と注意点
生前に実家の名義を子供に変更する(生前贈与)と、原則として贈与税が課税されます。
実家の名義が子供になっていれば、将来的に子供が自宅として利用したり、自由に売却したりすることが可能になります。名義変更の手続きは法務局で行う所有権移転登記、いわゆる「贈与登記」です。生前贈与は、親が認知症になり施設に入居する際など、住む人がいなくなった実家をスムーズに売却できるというメリットもあります。
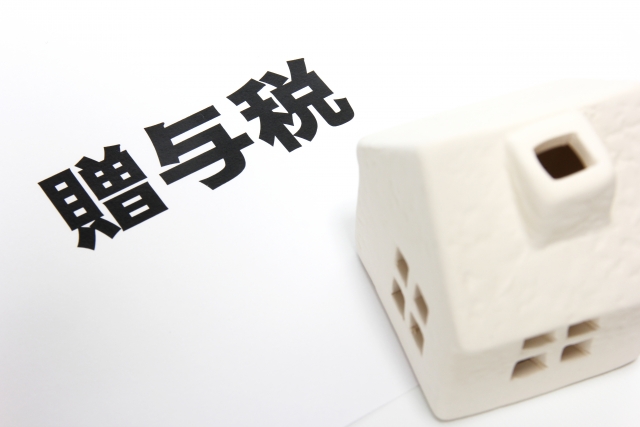
しかし、「贈与登記」には登録免許税のほか、贈与税や不動産取得税といった税金が発生します。特に、生前に実家の名義を変更すると、高額な贈与税が課税される可能性があります。
実家を贈与する場合、生前の「贈与税」と、親が亡くなった後の相続時にかかる「相続税」を試算し、どちらの税負担が少なくなるかを比較検討することが重要です。
「生前贈与」とは、ご存命中に配偶者や子供などに不動産(住宅や土地)、現金、預貯金などの財産を贈与することです。生前に財産を贈与することで、相続時の財産を減らし、相続税の節税効果が期待できますが、代わりに贈与税が課税されます。
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式があります。
暦年課税(暦年贈与)
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた人一人あたり110万円までの贈与は非課税となります(基礎控除)。
暦年課税による贈与税の計算方法
贈与税額=(贈与財産の合計額−基礎控除額(110万円))×税率−速算控除額
※税率は、贈与額に応じて定められた速算表を用いて計算します。
不動産の贈与についても贈与税は課税されます。この場合、課税対象となるのは不動産の売買価格ではなく、一般的に売買価格よりも低い「相続税評価額」です。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産またはその取得資金を贈与する場合、2,000万円まで贈与税が非課税となる「配偶者控除」の特例が利用できます。この特例は、暦年課税の基礎控除110万円と併用できるため、合計で2,110万円まで非課税で贈与することが可能です。ただし、この特例の適用には一定の要件があります。
重要な注意点
- 生前贈与は相続税対策として有効な場合がありますが、贈与税や不動産取得税、登録免許税などのコストも考慮する必要があります。
- 相続時精算課税を選択した場合、贈与時には贈与財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除が適用されますが、相続時には贈与時の価額で相続税が計算されます。どちらの課税方式が有利かは、個々の状況によって異なります。
- 不動産の評価額は複雑なため、専門家(税理士など)に相談することをおすすめします。
住宅取得等資金の贈与は最大1,000万円まで非課税に!【2026年12月31日まで】
18歳以上の方が、直系尊属(父母や祖父母)から住宅の新築、取得、または増改築等のための資金を贈与された場合、「住宅取得等資金の贈与の非課税特例」を活用することで、贈与税が軽減されます。

省エネ等住宅の非課税枠が500万円アップ
この特例により、受贈者一人あたり、省エネ等住宅の場合は最大1,000万円、それ以外の住宅の場合でも最大500万円までの贈与額が非課税となります。さらに、この非課税枠は、暦年贈与の基礎控除110万円と併用することが可能です。
2026年12月31日までの贈与については、以下のいずれか1つの基準を満たす住宅の場合、非課税となる贈与額が通常よりも500万円増額され、1,000万円までとなります。
- 省エネ性能: 断熱等性能等級5以上、または一次エネルギー消費量等級6以上
- 耐震性能: 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免震建築物
- バリアフリー性能: 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
既存住宅・増改築における特例
既存住宅の取得や増改築の場合でも、一定の条件を満たせば特例の対象となります。
- 2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2024年6月30日までに建築された住宅で、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であれば、非課税となる贈与額が500万円アップします。
- 昭和57年1月1日以後に建築された中古住宅で、取得後に耐震改修を行い、贈与の申告期限までに耐震基準を満たすことを証明できる場合も、特例の適用を受けることができます。

この特例を活用することで、住宅取得の際の資金援助を税負担を抑えながら行うことが可能です。
実家を耐震改修や省エネ改修などリフォームする場合はこちらのリフォーム会社一括見積もりサイトで、エリアごとの実家リフォームの最安値を出してリフォーム会社を選ぶといいでしょう。
「省エネの高い住まい」にする際、新築やリフォームで利用できる補助金制度の一つに「⼦育てグリーン住宅支援事業」(旧:子育てエコホーム支援事業)があります。この制度を活用すれば、住宅の初期費用を抑えながら、快適で環境に優しい住まいを実現することが可能です。
贈与税が非課税に?相続時精算課税制度の新たな非課税枠【2024年1月以降】

2024年1月1日から、相続時精算課税制度が改正され、年間110万円までの贈与については贈与税が非課税となり、贈与税の申告も不要となりました。これは、暦年贈与の基礎控除と同様の非課税枠が、相続時精算課税制度にも新たに設けられたものです。
相続時精算課税制度は、生前贈与を行う際に2,500万円までの特別控除が適用され、贈与時には贈与税が課税されない(または特別控除内で済む)制度です。しかし、贈与者が亡くなった際には、生前贈与した財産の価額を相続財産に合算して相続税を計算し、まとめて納税する必要があります。
この2,500万円の特別控除は、複数回にわたる贈与の累計額で計算されます。現金だけでなく、住宅や土地などの不動産が贈与された場合にも利用可能です。
相続時精算課税制度の適用要件(贈与者・受贈者)
- 贈与者: 贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母
- 受贈者: 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫で、贈与者の推定相続人 贈与者と受贈者の関係が、「親子」または「祖父母と孫」であること
※2022年3月31日以前の贈与により財産を取得した場合は20歳以上
重要な注意点:非課税枠と特別控除の関係
今回の改正で導入された年間110万円の非課税枠は、2,500万円の特別控除とは別枠で適用されます。つまり、年間110万円までの贈与については、特別控除の枠を消費せずに行うことができ、相続時の相続財産への加算も不要となります。
ただし、年間110万円を超える贈与については、2,500万円の特別控除の対象となります。この特別控除の累計額が2,500万円を超えた場合、超過額に対して一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度は、生前の財産移転を円滑にするための制度ですが、安易に選択すると相続税の負担が増える可能性もあります。制度の内容を十分に理解し、自身の状況に合わせて慎重に検討することが重要です。
「家族信託」で実家の財産管理をスムーズに!認知症対策にも
認知症などにより意思表示能力が低下すると、大切な実家や預貯金などの財産が凍結され、管理や処分が困難になることがあります。
そこで注目されているのが「家族信託」です。これは、ご自身の財産を信頼できるご家族に託し、管理・処分を任せることのできる財産管理の手法です。

判断能力が低下した場合に備え、ご自身の希望に沿った財産管理や相続対策を、信頼できるご家族に託す仕組みです。
例えば、「家族信託」を活用して実家の管理を長男に託しておけば、実家を所有する父親が認知症などで意思表示が難しくなった場合でも、受託者である長男の権限で実家を売却することができます。
売却によって得た資金は信託口座で管理され、父親の医療費や介護施設の入居費用など、必要な用途に柔軟に活用することが可能です。
親御さんがご存命であれば容易に解決できることも、亡くなられた後では複雑な相続問題に発展するケースも少なくありません。「家族信託」は、このような将来的なリスクへの備えとしても有効な手段と言えるでしょう。
親が亡くなった実家(空き家)の相続と売却:後悔しないためのポイント

親御様が亡くなられた場合、相続が発生し、実家(空き家)を相続される方が多くいらっしゃいます。思い出の詰まった実家ですが、長期間放置すると管理の手間や費用、税金がかさむため、早めの対応が重要です。
空き家放置のリスク:固定資産税が最大6倍に
空き家を放置すると、「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。「特定空き家」に認定されないよう注意が必要です。
固定資産税の特例:更地にすると適用外に
通常、空き家が建つ土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が6分の1に軽減されます。建物を解体して更地にすると建物の固定資産税はなくなりますが、この特例が適用されなくなるため、土地の固定資産税が増加し、結果的に固定資産税の総額が上がる点に注意が必要です。
維持管理の負担と売却のメリット
住まなくなった実家(空き家)は、そのままにしておくと維持管理に時間と費用がかかります。相続した空き家を「売却」することで、これらの負担から解放されます。
空き家の活用方法:賃貸や駐車場という選択肢
売却以外にも、空き家を活用する方法があります。
- リフォームして賃貸に出す: 安定した収入が期待できます。
- 解体して駐車場にする: 土地を有効活用できます。
実家を賃貸にするためのリフォームをする場合はこちらのリフォーム会社一括見積もりサイトで、エリアごとの実家リフォームの最安値を出してリフォーム会社を選ぶといいでしょう。
売却の第一歩:相続登記
親御様名義のままでは実家を売却できません。まずは、お子様への名義変更(相続登記)を行う必要があります。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(マイホームを売ったときの特例)」を適用できる!
例えば、父と子が同居していて、父が亡くなり、子が転居のため、相続したその家に住まなくなった日から3年を経過する日の年の12月31日までに売却した場合、要件を満たせば適用できます。売却益が出た場合の譲渡所得から所有期間の長短に関係なく最高3,000万円まで控除できます。「取得費加算の特例」とも併用可能です。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、日本の所得税法に基づく制度で、一定の条件を満たす場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるものです。この特例を適用することで、譲渡所得税の負担を軽減することができます。
特例の概要
- 適用対象:個人が自己の居住用財産(自宅)を売却した場合。
- 控除額:譲渡所得から最大3,000万円を控除。
- 適用回数:同一の個人については、1年間に1回まで。
※この特例の適用を受けた後、3年間は再度この特例を受けることができません。
適用条件
- 譲渡財産:譲渡する財産が自己の居住用であること。
- 所有期間:原則として、譲渡する財産を5年以上所有していること。
- 居住期間:譲渡する財産に実際に居住していること。
- 譲渡後の居住:譲渡した年の翌年12月31日までに居住を辞めること。
- 親族等への譲渡:親族等への譲渡は適用外となります。
- その他:特定の事業用資産を含む場合や、贈与を含む特定のケースには適用されないことがあります。
具体例
例えば、譲渡所得が4,000万円の場合、この特例を利用すると、4,000万円から3,000万円を控除し、1,000万円が課税対象となります。
この特例を利用する際には、確定申告が必要ですので、詳しい手続きや条件については、税務署や税理士に相談するとよいでしょう。
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を使ってお得に売却!
1人暮らしをしていた親が亡くなり、空き家になった実家を子供が売却する場合には、譲渡所得から最高3000万円まで控除が受けられる特例があります。
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、日本の税制において、一定の要件を満たす空き家を譲渡した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができる特例です。この特例は、空き家問題の解消を目的として設けられています。
特例の概要
- 適用対象:相続により取得した空き家や、空き家を取り壊して更地にした土地。
- 控除額:譲渡所得から最大3,000万円を控除。
- 適用期間:平成28年4月1日から令和7年12月31日までの譲渡。
適用条件
- 相続日:被相続人が亡くなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
- 被相続人の居住用財産:被相続人が一人で居住していた住宅であり、昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
- 譲渡時の状態:
- 住宅としての利用がされていないこと。
- 一定の耐震基準を満たすか、取り壊して更地にすること。
- 譲渡先:親族等への譲渡は適用外。
- 譲渡価格:譲渡価格が1億円以下であること。
具体例
例えば、相続によって取得した空き家を売却し、譲渡所得が4,000万円の場合、この特例を利用すると、4,000万円から3,000万円を控除し、1,000万円が課税対象となります。
この特例を利用する際には、確定申告が必要です。また、適用条件や手続きについては税務署や税理士に相談することをお勧めします。
老人ホームに入所していた親が、空き家を残して亡くなられた場合も、空き家を取り壊して更地にして売却した場合も対象です。

相続後に売却することで、売却金を相続税に充てることができます。
特例は相続人ごとに適用できます。
例えば3人の子供が相続した場合、適用対象者毎に3,000万円までの適用が可能になりますので
3人の場合は最大で3,000万円控除×3人=9,000万円相当の控除が可能になります。
換価分割が行える

実家は大きな資産になりますが、複数の相続人で分けることができません。複数の中から相続する人がすんなりと決まれば良いですが、相続人どうしでトラブルに発展することにもなりかねません。
分割できない実家を現金化することで相続人全員に分割することができます。売却で得た現金を法定相続人の間で均等に分割する相続方法です。
また、遺産を分割する方法に、特定の財産を相続した人が、他の相続人に代償金を支払う方法の代償分割、実家や預貯金や株式など現物そのままを相続する方法の現物分割があります。
「小規模宅地等の評価減の特例」を使って敷地の評価を下げる!
自宅の敷地については相続税評価額を下げられる特例です。配偶者、同居親族、又は賃貸に住んでいる別居親族が自宅を相続し、一定の要件を満たした場合、自宅の敷地のうち330㎡までの部分について、相続税評価額を80%減額できるという制度です。宅地等の評価減の特例は、相続税を安くするための制度です。
ポイント
- 居住用宅地:
- 評価額を80%減額
- 対象面積:330㎡まで
- 事業用宅地:
- 評価額を80%減額
- 対象面積:400㎡まで
- 貸付事業用宅地:
- 評価額を50%減額
- 対象面積:200㎡まで
具体例
1億円の居住用宅地(300㎡)を相続する場合、80%減額されて課税額は2,000万円になります。

この特例を利用すると、相続税が大幅に減ります。
我が家は駐車場経営で収益を得ています。空いてる駐車場スペースをアキッパで貸し出しして毎月5,000円程の収益になっています。akippaと特Pではどちらがお得なのかこちらの記事をご覧ください。
我が家は駅南で駅まで自転車で15分のところです。立地条件が良ければ毎月5,000円以上の収益は可能です。2年間運営してトラブルは今のところ無いです。少しでも収益が出るのは嬉しいですね。
「取得費加算の特例」は相続から3年10カ月以内に使える!
不動産に限らず、相続により取得した不動産や株式などの財産を売却した場合に、その不動産や株式などにかかった相続税を、売却した財産の取得費に加算することができるという特例です。その分、譲渡所得税が減額されることとなります。この特例を使うには、相続税の申告期限(原則、相続開始後10カ月)から3年以内に売却する必要があります。
取得費加算の特例は、相続や遺贈で取得した財産を譲渡した場合に、相続税の一部を取得費に加算できる制度です。これにより、譲渡所得税を軽減することができます。
ポイント
- 対象:相続や遺贈で取得した財産を譲渡する場合。
- 加算額:相続税の一部を取得費に加算。
- 適用期間:相続開始日から3年10ヶ月以内に譲渡する場合。
具体例
- 相続で取得した土地を譲渡。
- 譲渡時の取得費に相続税の一部を加算し、譲渡所得を減少させる。
利用手続き
- 譲渡所得の確定申告時に、取得費加算の特例を申請。

この特例を利用することで、譲渡所得税を減らし、税負担を軽減することができます。
「訳あり物件を本当に買い取ってもらえるのか?」「詐欺ではないのか?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。信頼できる業者なら売却したいけれど、安心して利用できるか心配ですよね。本記事では、「訳あり物件買取プロ」の特徴や口コミを徹底解説し、その信頼性について詳しくご紹介します。安心して物件を売却するためのヒントを知りたい方は、ぜひご覧ください!
まとめ

日本の社会では、空き家問題が深刻化しています。特に、親が高齢になり、実家が空き家になるケースが増えています。このような状況において、実家を売却するタイミングは重要な決断となります。
相続前でも相続後でも特別控除が利用できれば同じ額の節税になります。ただし、「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」の場合は適応要件が細かくて適応できない場合があります。相続前に適応可能な特例を確認して、親がまだ元気なうちに話し合うことで最適な売却ができます。
相続前と相続後ではどちらで売却するのが得なのかは、一概にどちらが良いとは言えません。使える特例の条件に合わせたタイミングで売却することが重要です。相続税のことを考えると、現金での相続よりも不動産での相続の方が相続税を抑えることができます。「相続税対策」という視点で考えるなら、答えは「相続後」です。なぜなら、不動産相続には税制上の優遇制度や特例があり、現金で相続するよりも税額が抑えられるからです。
実家の売却を親の生前に行うか、相続後に行うかは、それぞれにメリットとデメリットがあります。親の意思を尊重しながら、家族全員が納得できる方法を選ぶことが重要です。
・親の健康状態と意思
・家族全員の合意
・不動産市場の状況
・税金面での影響
これらのポイントを考慮して、最適なタイミングを見極めましょう。

最終的には、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することをお勧めします。

監修者:河田憲二(株式会社AlbaLink 代表取締役)
「全国の空き家ゼロに」を掲げ、空き家や訳あり物件に特化した買取業者(株式会社AlbaLink)を営む。
同社が運営しているサービスサイトである「訳あり物件買取プロ」の運営責任者も務めています。同社は東京証券取引所の東京プロマーケット市場に上場している。(証券コード:5537)
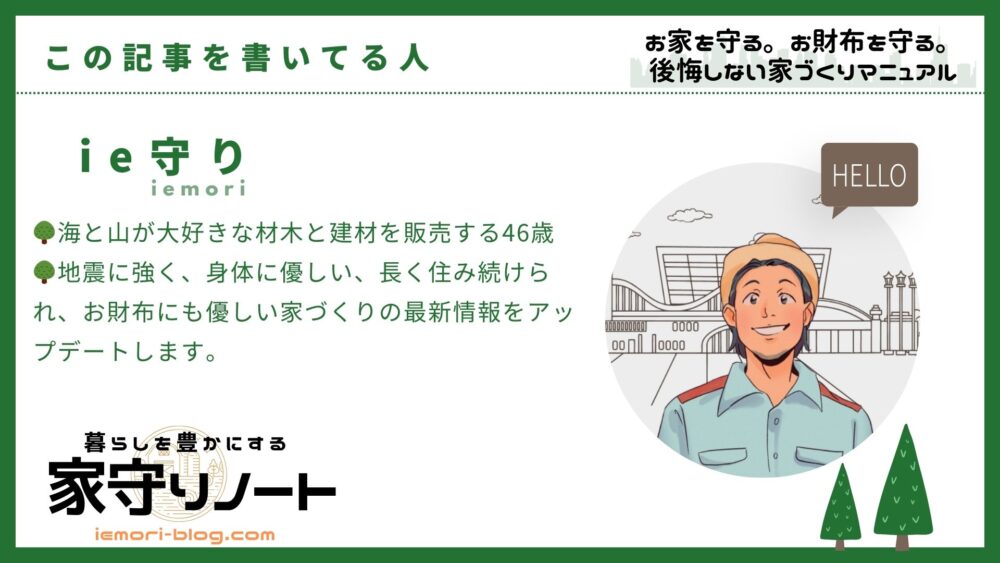
この記事に関して質問や相談、リクエストなどあればお問い合わせいただくか、(X)Twitterで DMください。お待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございました。
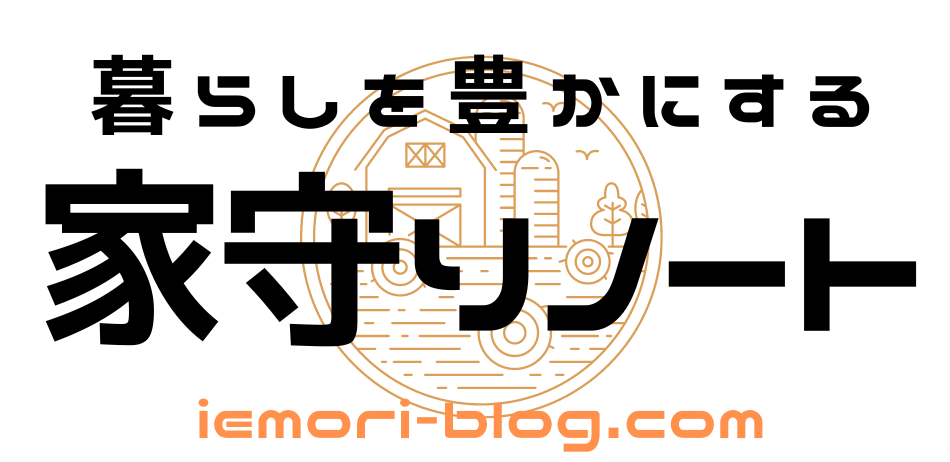
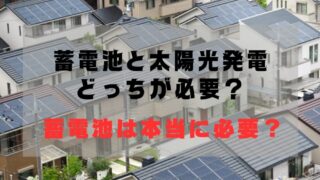
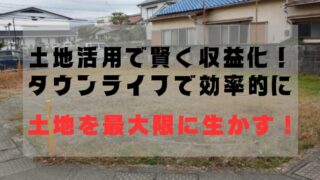
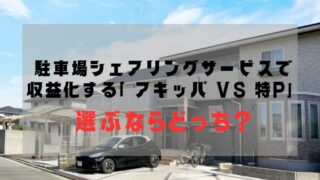
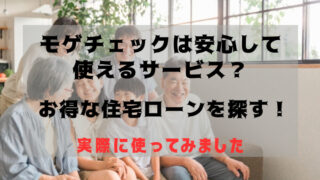
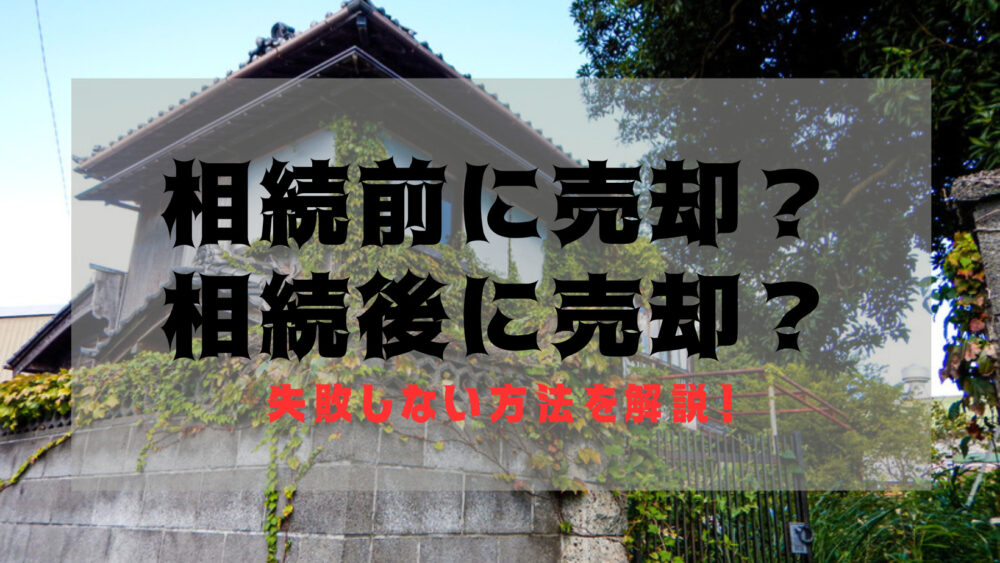
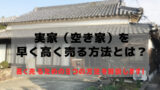
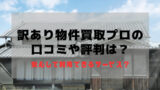

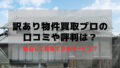
コメント