「耐震等級3って、実際どれくらい意味があるの?」「地震保険が安くなるって聞いたけど、本当にそんなに違うの?」家づくりを考え始めると、こんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。実は、耐震等級3の家にすることで、地震保険の保険料が最大50%割引されるだけでなく、住宅ローンの金利優遇まで受けられる可能性があります。つまり、初期コストは少し上がっても、**長い目で見るとかなりの“おトク”**になるケースもあるのです。
この記事では
などを、住宅業界のプロ目線でわかりやすく解説します。「後悔しない家づくり」のために、ぜひ最後までご覧ください。
- 耐震等級とは?1・2・3の違いをわかりやすく解説
- 「地震に強い家」の構造の特徴とは?
- 「耐震等級」を選ぶ際のポイント
- 耐震等級3は「許容応力度計算」で構造計算する!
- 耐震等級3にすると住宅コストは上がるの?
- 耐震等級3の家にすると、なぜ地震保険が安くなるのか?
- 住宅ローン金利も優遇?耐震等級3の家にすると得する理由
- 耐震等級3の家を建てるには?取得の流れと注意点
- 地震保険の「耐震等級割引」で保険料を大幅に節約!
耐震等級とは?1・2・3の違いをわかりやすく解説
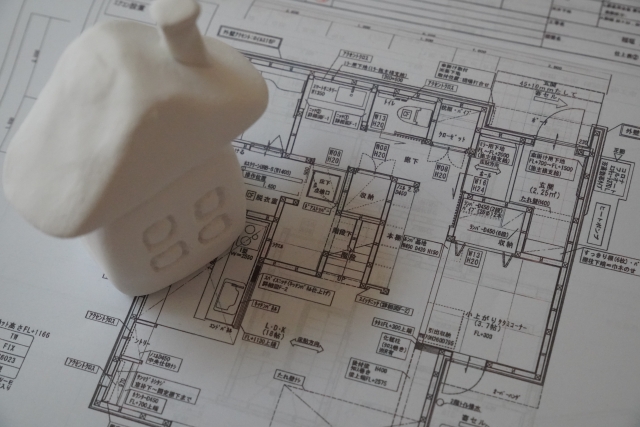
耐震等級とは、建物の地震に対する強さを示す指標で、1~3の3段階で評価されます。これは国の「住宅性能表示制度」に基づくもので、数字が大きくなるほど耐震性能が高くなります。ここでは、それぞれの耐震等級の意味と、どれだけの揺れに耐えられるのかをわかりやすく解説します。
構造設計をするうえで、間取りなどのプランニングと一緒に検討が必要なところが「耐震等級」です。安心して住める家を選ぶためにも、耐震等級の違いを理解し、適切な選択を行うことが大切です。
耐震等級1は「建築基準法」レベル
耐震等級1は、現行の建築基準法に適合した最低ラインの耐震性能です。具体的には、数百年に一度の大地震(震度6強〜7程度)で「倒壊・崩壊しない」レベルとされています。ただし、「住み続けられる」とは限らず、大きな被害を受ける可能性がある点に注意が必要です。1981年の6月1日以降に建てられたすべての建物が耐震等級1以上に該当します。
基準: 現行の建築基準法に準拠した最低限の耐震性能。
耐震性能: 数十年に一度発生する程度の中規模地震(震度5強程度)では損傷を受けず、数百年に一度発生する大規模地震(震度6強から7程度)でも倒壊や崩壊を防ぐことが目標。
適用: 建築基準法に適合しているすべての新築住宅がこの等級に相当します。
耐震等級2は「長期優良住宅」レベル
耐震等級2は、等級1の1.25倍の耐震強度を持ち、主に学校や病院などの避難場所に指定される建物と同等の強度です。長期優良住宅に認定されるには、最低でもこの耐震等級2が必要とされます。ただし、震度7クラスの地震が繰り返し発生した場合は、倒壊リスクが残るという点が熊本地震の事例で明らかになりました。数十年に一度の地震(震度6強〜7)の後でも、軽度の補修を行えばその後も長く住み続けられる基準になります。

基準: 耐震等級1の1.25倍の耐震性能。
耐震性能: 学校や病院、避難所などの公共施設に求められる耐震性能を満たす。
メリット: 耐震等級1に比べて耐久性が向上し、災害時にも重要な機能を果たすことが期待されます。
耐震等級3は「防災拠点と同等」レベル
耐震等級3は、等級1の1.5倍の耐震性能を持ち、消防署や警察署など、防災拠点となる重要施設と同じ基準で設計された建物です。この等級は、震度7クラスの大地震が連続して起きても倒壊しないレベルの強度を持つとされ、住宅としては最も安心できる耐震性能です。震度6強〜7程度の地震が起きても軽微な補修を行えばその後も長く住み続けられる基準で設計されています。
基準: 耐震等級1の1.5倍の耐震性能。
耐震性能: 警察署や消防署、災害対策本部など、災害時に機能を維持することが求められる建物の基準です。
メリット: 最高の耐震性能を誇り、地震の後でも簡単な補修で居住を続けられる可能性が高い。
👉現在、地震保険や火災保険への加入を検討されている方、または既にご加入で追加・見直しを考えている方は、複数の保険会社をしっかりと比較検討し、最もお得なプランを選びましょう。
▶ 熊本地震で証明された「等級3の強さ」
2016年の熊本地震では、震度7が2回発生しました。この地震での被害状況は、耐震等級ごとの違いが明確に表れました。
- 耐震等級1の住宅:倒壊・半壊の被害が多数
- 耐震等級2の住宅:倒壊した事例あり(繰り返しの揺れに弱い)
- 耐震等級3の住宅:倒壊ゼロ。大きな損傷も少数
実際、熊本県益城町の調査では、耐震等級3の木造住宅で倒壊した例は確認されていませんでした。
📊 「等級ごとの耐震強度と倒壊リスク」図解例
| 耐震等級 | 強度(基準法比) | 建物例 | 倒壊リスク(熊本地震時) |
|---|---|---|---|
| 等級1 | 基準法レベル(1.0) | 一般的な住宅 | 高い |
| 等級2 | 1.25倍 | 長期優良住宅、学校 | 中程度 |
| 等級3 | 1.5倍 | 防災拠点レベルの家 | 極めて低い |
「地震に強い家」の構造の特徴とは?

2016年に発生した熊本地震では、震度7の揺れがわずか28時間の間に2度も発生しました。
この地震により、「耐震等級2」の住宅でも倒壊が確認され、建築基準法レベルの「耐震等級1」や、長期優良住宅レベルの「耐震等級2」では、震度7クラスの地震が繰り返されると倒壊リスクが高まることが明らかになりました。
一方で、最も耐震性能が高い「耐震等級3」の住宅は、大きな被害を受けた事例がほとんどなく、軽微な補修で住み続けられたケースが多数報告されています。これは、地震に強い家=耐震等級3の構造で建てられた家であることを証明しています。
それでも「耐震等級3」の価値が知られていない現実
ところが、多くの方が今でも「耐震等級3」の価値を知らず、知らないうちに地震リスクの高い家を選んでしまっているのが現状です。家族の命や財産を守るには、倒壊しない家=耐震等級3の住宅が欠かせません。
さらに、耐震等級3にすることで、
- ✅ 地震保険が最大50%割引になる
- ✅ 住宅ローンの金利優遇を受けられる

など、お金の面でも大きなメリットがあることをご存じでしょうか?
「耐震等級3って高そう…」は過去の話
「でも、耐震等級3って建築費が高いんじゃないの?」と思われるかもしれません。確かに以前はオプション扱いで、追加コストが必要な会社も多くありました。しかし最近では、耐震等級3を標準仕様として採用する住宅会社も増加しており、コストを抑えて建てることが可能になってきています。
家づくりで最も大切なのは、倒壊しない構造を選ぶこと
耐震等級3の家は、消防署や警察署など防災拠点と同じレベルの耐震性を持ち、大地震のあとでも、大規模な補修をせずに住み続けられる可能性が高くなります。家族の命と暮らしを守るために、何よりも大切なのは「地震で壊れない家を選ぶこと」です。
その鍵を握るのが、「耐震等級3」の構造です。
等級3の住宅であれば、たとえ震度7の大地震が起きたとしても、補修のみで住み続けられるケースが多く報告されています。
設計段階での確認が「後悔しない家づくり」の第一歩

耐震等級には「1〜3」のランクがあり、それぞれに明確な耐震性能の差があります。信頼できる住宅会社であれば、お客様の要望に応じて、適切な等級を提案してくれるはずです。ただし、実際には耐震等級3を標準採用している会社はまだ多くはありません。
また、家が上棟してからでは構造の変更がほぼ不可能になるため、設計プランが固まる前に、必ず耐震等級について確認することが大切です。
「耐震等級」を選ぶ際のポイント
居住者の安全: 耐震等級が高いほど、居住者の命や財産を守る確率が高まります。
コスト: 耐震等級が上がると、構造の補強や材料の品質向上により建設コストが増加する場合があります。ただし、地震保険の割引や住宅ローンの優遇措置を受けられるため、長期的に見て経済的なメリットが得られることもあります。
将来の安心: 日本は地震の多い国であり、耐震等級の高い将来住宅に住むことは、将来的なリスクを軽減し、安心して暮らすための重要な要素となります。
耐震等級3を選ぶことは、最大限の安全と安心を確保し、将来的なリスクを軽減するために有効な選択と言えるでしょう。

耐震等級1~3の基準を知ってどうでしょうか?
この「耐震等級」のことを知った上で、あえて耐震等級1で建てたいと思う人は少ないでしょう。誰もが消防署や警察署と同じ、防災の拠点レベルの耐震等級3で建てたくなるはずです。「私も、家を建てる当時に耐震等級3の重要性を理解していれば、迷わず耐震等級3で建てていたでしょう。」耐震等級3で建てるには、構造計算が必要ですが、この構造計算にも3通りの方法があります。それぞれの計算方法を理解することで、家の耐震性能をより確実に高めることができます。
耐震等級3は「許容応力度計算」で構造計算する!
耐震等級3の構造計算を行う場合には、以下の3つの計算方法があります。
- 建築基準法仕様規定による耐震等級3
- 品確法における性能表示計算による耐震等級3
- 建築基準法許容応力度計算による耐震等級3

これらの計算方法によって、耐力壁の量や柱の配置が異なり、それが建物の耐震性に大きく影響します。
構造計算とは?

構造計算とは、建物の耐震性や強度を確認するための計算で、柱・梁・桁・壁の配置や強度が、どの程度の地震に耐えられるか評価するものです。その目的は、地震や台風などの自然災害に関して建物が倒壊しないように、安全性を確保することにあります。
3階建て以上の建物には構造計算が義務付けられていますが、2階建て以下の木造住宅では「四号特例」により義務化されていません。そのため、多くの住宅で詳細な構造計算が行われていないのが現状です。
四号特例とは?
「四号特例」とは、建築士が設計する場合、確認申請時に構造計算書が不要となる制度です。 この制度提出により、9割以上の木造住宅が簡易な仕様規定(壁量計算、配置バランスの確認など)に基づいて設計されています。
各計算方法の特徴は以下の通りです。
建築基準法仕様規定:壁量計算・四分割法・N値計算といった簡易的な計算方法。
品確法における性能表示計算:住宅品質確保促進法(品確法)の基準に基づいた計算方法。
建築基準法の許容応力度計算:外力を受けた際に部材にかかる力(応力度)が、部材の許容範囲内であることを確認する計算法。
「許容耐力度計算」による耐震等級3を選ぶべき理由
許容応力度計算は、現在の住宅設計では一般的ではなく、スパン表を用いた簡易な計算方法が多く採用されています。ただし、家の安全性を最大限に高めるためには、「許容耐力計算による耐震等級3」を選択することが重要です。建築計画の段階で、どの耐震等級を目指すか早めに決めましょう。後から変更が難しくなることが多く、耐震等級によって柱の位置や間取りの変更が必要になる場合もあります。


自宅の耐震等級を把握しておくことは、長く安心して過ごすために重要なポイントです。
耐震等級3にすると住宅コストは上がるの?

「耐震等級3」を取得するにはまず、構造計算費用や耐震性能向上のための建築コストが増加します。具体的にどれくらいコストアップするでしょうか?ここでは目安となる金額をお伝えしますので、参考にしてください。
耐震等級3にするためのコスト
1. 構造計算費用(許容応力度計算)
30坪ほどの2階建て住宅の場合、約15~20万円前後の費用がかかります。
2. 建築コストの増加
耐震等級1から耐震等級3に性能を上げる場合、以下のようなコストアップが発生します。
- 構造材の補強(梁や桁の大型化、柱の増加、合板・面材の追加) →約30万円前後
- 基礎の強化(より強い木構造を支えるための基礎補強) →約50万円前後
これらを合わせると、耐震等級3にするための総コストアップは約100万円前後となります。
コストアップを補う割引
耐震性能を向上させることで住宅コストがかかっても、以下のような割引があるため、最終的な支払額を下げることができます。
✅地震保険の割引:耐震等級3の住宅では、地震保険の保険料が最大50%割引されます。
✅フラット35Sの検討:住宅ローン「フラット35S」の金利引き下げを活用することで、長期的な支払い額を減らすことができます。
例:地震保険の割引とフラット35Sの検討を合わせて、約140万円の節約ができるため、耐震等級3の住宅の方がトータルでお得になる可能性が高いです。
✅長期優良住宅による補助金:耐震等級3の住宅が長期優良住宅として認定されると、「⼦育てグリーン住宅支援事業2025」などを活用でき、約80万円の助成金を受けられることがあります。
地震保険の割引や、フラット35Sの検討見直し、長期優良住宅補助金を活用することで、最終的な総支払額が安くなることがあります。これを活用すれば、耐震等級3の住宅を建てるコストは、結果的により抑えることができるでしょう。

家族の安心を守り、財産を保護するためにも、耐震等級3での家づくりを強くオススメします。
耐震等級3の家にすると、なぜ地震保険が安くなるのか?
地震に強い家に住みたいと思っても、「それってコストが上がるんでしょ?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。でも実は、耐震等級3の家にすることで「地震保険料が大幅に割引」される制度があるのをご存じでしょうか?これは国が定めた**「地震保険料割引制度」**によるもので、建物の耐震性能が高いほど保険料が安くなる仕組みです。

地震保険料の割引制度(建築年・耐震等級による)
地震保険には、建物の「耐震性能」に応じて最大50%まで保険料が割引される制度があります。主に以下の4つの条件があり、それぞれ割引率が異なります。
| 割引の種類 | 内容 | 割引率 |
|---|---|---|
| 耐震等級割引 | 耐震等級1・2・3に対応した建物(品確法による評価) | 最大50% |
| 免震建築物割引 | 地震の揺れを建物に伝えない「免震構造」の住宅 | 50% |
| 耐震診断割引 | 耐震診断を受け、一定基準を満たした場合 | 10% |
| 建築年割引 | 1981年6月1日以降の「新耐震基準」で建築された住宅(戸建て等) | 10% |
この中で**最も割引率が高いのが「耐震等級3」**の住宅です。
最大50%オフになる「耐震等級割引」の仕組み
「耐震等級割引」は、**国が定めた住宅性能表示制度(品確法)**に基づいて評価された建物に適用されます。具体的な割引率は以下のとおりです。
| 等級 | 耐震性能の強さ(建築基準法比) | 地震保険の割引率 |
|---|---|---|
| 等級1 | 建築基準法レベル | 割引なし |
| 等級2 | 等級1の1.25倍 | 30%割引 |
| 等級3 | 等級1の1.5倍 | 50%割引 |
つまり、耐震等級3の住宅なら、同じ保険内容でも半額で加入できるという非常に大きなメリットがあります。しかもこの割引は保険契約期間中ずっと続くため、保険料を長期的に抑えることができます。
具体的な保険料比較シミュレーション(例:等級1と3の違い)
では、実際にどれくらい金額に差が出るのか、シミュレーションしてみましょう。
- 建物:木造2階建て・建築価格2,000万円
- 地震保険:保険金額1,000万円(建物部分)
- 保険期間:1年、長期契約なし、東京都エリア
▼ 等級ごとの地震保険料(概算)
| 等級 | 年間保険料(概算) | 割引率 | 差額(等級1との比較) |
|---|---|---|---|
| 等級1 | 約28,000円 | 0% | — |
| 等級2 | 約19,600円 | 30% | 約8,400円の節約 |
| 等級3 | 約14,000円 | 50% | 約14,000円の節約 |
10年間加入した場合、14万円近い差が出ることもあります。しかも火災保険とセットで加入するのが一般的なため、実際はもっと大きな金額の違いにつながるケースもあります。
▶ 火災保険+地震保険を安くするなら一括見積もりが便利!
とはいえ、地震保険は火災保険とのセット契約が必須。だからこそ、「保険料を安くしたい」「必要な補償はつけたい」と考えている方には、 「火災保険一括見積もりサービス」の利用が効果的です。
✅ 数社の保険料や補償内容を比較
✅ 最安プランや割引条件もすぐにわかる
✅ 耐震等級割引の対象かも確認できる
下記リンクから、簡単に見積もり・比較ができます👇
火災保険の比較はこちらから住宅ローン金利も優遇?耐震等級3の家にすると得する理由
耐震等級3の住宅は、地震保険が安くなるだけではありません。実は、住宅ローンの金利まで優遇される制度があるのです。中でも、国が支援する「フラット35」では、一定の技術基準を満たした住宅に対し、金利を引き下げる優遇措置を設けています。
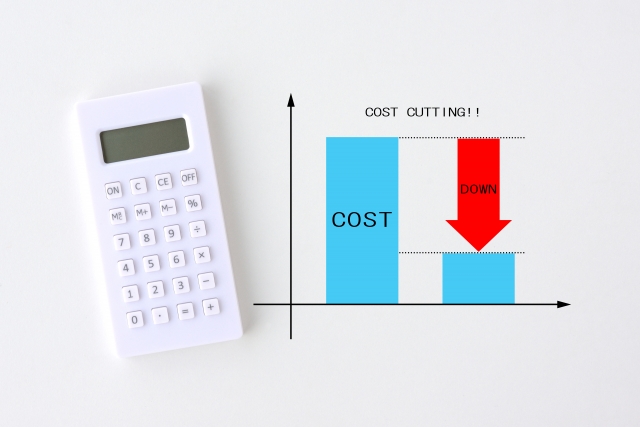
「フラット35」の技術基準に適合すると金利優遇
「フラット35」は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する全期間固定金利型の住宅ローンです。
この制度には、一定の条件を満たすと金利を引き下げてもらえる**「フラット35S」**という優遇制度があります。フラット35Sでは、下記のいずれかの基準に適合することで、借入当初の5年または10年間、金利が引き下げられます。
フラット35Sの金利引下げ条件(技術基準例)
| 評価基準 | 対象住宅例 |
|---|---|
| 耐震性 | 耐震等級2以上(※等級3であれば確実に該当) |
| 省エネ性 | 認定低炭素住宅・ZEHなど |
| 劣化対策 | 劣化対策等級3に適合 |
| バリアフリー性 | バリアフリー等級3など |
この中でも耐震等級3は高確率で対象となる条件です。
「長期優良住宅」や「低炭素住宅」の加点要素
「長期優良住宅」や「低炭素住宅」に認定されると、フラット35Sに加えて他の補助制度とも連動しやすくなります。
- ✅ 長期優良住宅:耐震等級2以上が必須 → 耐震等級3なら高評価
- ✅ 認定低炭素住宅:省エネ性能重視だが、耐震等級が加点対象になる自治体も
- ✅ 補助金(例:こどもエコすまい支援事業など)も組み合わせ可
つまり、耐震等級3の家を建てることで、金利+補助金という二重の恩恵を受けられる可能性があります。
実際にどれだけ金利差が出る?年間支払い額の違い
では、実際に「フラット35S」の金利優遇でどのくらい得するのか、具体的なシミュレーションを見てみましょう。
【比較条件】
- 借入額:3,500万円
- 借入期間:35年(全期間固定)
- 通常金利:1.60%
- 優遇金利(フラット35S):1.35%(10年間0.25%引下げ)
- 返済方法:元利均等・ボーナス払いなし
▼ 支払額の比較(年間)
| 内容 | 通常金利(1.60%) | 優遇金利(1.35%) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 初年度の年間支払い額 | 約1,432,000円 | 約1,350,000円 | 約82,000円お得 |
| 10年間の支払い総額 | 約14,320,000円 | 約13,500,000円 | 約82万円お得 |
※実際の金利や金融機関により差があります。詳細は見積もり推奨。
▶ 金利の違いは長期で見れば数十万円~100万円以上の差に!
耐震等級3に対応するだけで、
- 10年間の金利差で約80万円の節約
- 保険料の割引と合わせると、トータルで100万円以上お得になるケースも
▶ まずは「フラット35Sの適用対象か」確認しよう!
住宅会社によっては、「耐震等級3」に対応していても、フラット35の技術基準を満たすための手続きや構造計算が省略されていることもあります。家づくりを始める際には
- 「この家はフラット35Sに対応できますか?」
- 「耐震等級3は取得予定ですか?」
といった確認を、設計段階で必ず行いましょう。
👉住宅ローンの最安金利がみつかるモゲチェックとは!口コミやデメリットも解説!
「どの銀行が自分に合うのかわからない」「金融機関を比較する時間がない」と悩んでいる方には、オンラインの住宅ローン比較ツールを活用するのがおすすめです。
耐震等級3の家を建てるには?取得の流れと注意点

「耐震等級3の家にしたい!」と思っても、自然にその仕様になるわけではありません。耐震等級3を取得するには、設計や申請の段階で明確な準備と対応が必要です。ここでは、等級3取得の流れや注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
設計時に「構造計算」が必須
耐震等級3の認定を受けるためには、**建物がどれくらいの地震力に耐えられるかを数値で証明する「構造計算」**が必要です。とくに木造2階建て以下の住宅は、通常「仕様規定」と呼ばれる簡易なルールで建築できますが、等級3を取得するには「許容応力度計算」などの詳細な構造計算が必要になります。
🔍構造計算の種類
| 構造計算の種類 | 耐震等級取得との関係 |
|---|---|
| 壁量計算(仕様規定) | 等級1程度まで(目安) |
| 許容応力度計算 | 等級2〜3の取得に必須 |
| 構造計算書 | 第三者機関へ提出して審査用に使用 |
✅ 設計事務所や工務店に「耐震等級3を取得する構造計算をお願いします」と明確に伝えることが重要です。
認定機関による申請と審査の流れ
耐震等級3を正式に取得するには、**住宅性能評価機関(登録住宅性能評価機関)**に申請を行い、評価書の発行を受ける必要があります。
▼ 取得までの基本的な流れ
- 設計段階で耐震等級3の構造設計を行う
- 設計内容を性能評価機関に申請
- 図面・構造計算書を審査される
- 「設計性能評価書」の発行(申請から2~3週間程度)
- 「建設性能評価書」の発行※現場検査つき(必要に応じて)
✅ 「設計性能評価書」だけでも保険割引やフラット35Sの要件を満たせるケースが多いですが、補助金などで求められる場合は「建設性能評価書」まで取得する必要があります。
対応してくれる工務店やハウスメーカーを選ぶポイント
耐震等級3を取得するためには、それに対応できる知識と実績がある住宅会社選びが非常に重要です。
✅ 見極めるポイント
| チェック項目 | 理由 |
|---|---|
| 「耐震等級3の取得実績がありますか?」と聞く | 実績がない会社だと、構造設計や申請でトラブルが出やすい |
| 「構造計算は誰がやりますか?」と確認する | 社内に構造設計者がいるか、外注かを把握できる |
| 「性能評価の申請は可能ですか?」と確認する | 性能評価まで対応してくれるかどうかは信頼度の大きな指標 |
| 「フラット35Sや補助金に強いですか?」と聞いてみる | 制度に詳しい会社は、施主にとって有利な提案ができることが多い |
👉 あなたに合った工務店の見つけ方を、プロの目線でまとめました。
「耐震等級3」に対応してくれる住宅会社を選びたい方へ、後悔しない家づくりのためには、信頼できる会社選びが最重要ポイントです。
地震保険の「耐震等級割引」で保険料を大幅に節約!
新築する建物の耐震等級によって、地震保険の保険料が「耐震等級割引」の対象となり、保険料を大きく抑えることができます。 耐震性の高い家を建てることで、安心して暮らせるだけでなく、経済的なメリットも享受できるのです。

耐震等級による割引率は以下の通りです。
●耐震等級3:保険料50%割引
●耐震等級2:保険料30%割引
●耐震等級1:保険料10%割引

防災拠点と同じレベルの耐震等級3の建物にすると、地震保険料が半額になります。
耐震等級による保険料の違い(例)
例、2000万円の家を建て、1年間の地震保険料が32,000円の場合、割引なしで35年間支払いと、合計支払額は1,120,000円になります。
耐震等級1の場合(10%割引)
32,000円 → 28,800円
28,800円 × 35年 = 1,008,000円
耐震等級3の場合(50%割引)
32,000円 → 16,000円
16,000円 × 35年 = 560,000円
耐震等級1と耐震等級3では、合計で448,000円の差額が生じます。
耐震等級3の家にすることで、耐震等級1よりも約45万円も地震保険料が安くなります。(35年間で見た場合)
長期的にお得な「耐震等級割引」
地震保険は、マイホームに住み続ける限り支払いが発生しますが、「耐震等級割引」を利用すれば、保険料を削減できます。 家の安全性を高めながら、経済的な負担を軽減するためにも、耐震等級3を選択する価値は十分あるでしょう。
保険選びは比較が重要!
私が火災保険に加入した際は、ファイナンシャル・プランナー(FP)による「ライフプランニング診断」を受け、その流れで火災保険に契約しました。その後、5年後に保険を見直して切り替えましたが、新築時に他の保険料と比較していれば、よりお得な契約ができた可能性があります。
保険料を比較して最適なプランを見つけよう!
地震保険や火災保険は、保険会社によって取り組んでいる割引制度が異なるため、複数社を比較することが重要です。
✅新規加入を検討中の方
✅現在加入中で乗り換えを考えている方
✅満期を迎えるにあたり検討している方

このような方は、ぜひ無料の保険見積もりサービスを利用して、最適なプランを見つけてください。
耐震等級3の家にすることで、地震に強いだけでなく、長期的な保険料にもつながります。地震保険や火災保険の追加・見直しを考えている方は、しっかり比較・検討して、お得に追加しましょう!
耐震等級3の家は、地震に強いだけでなく、長期的な保険料の節約にも繋がります。現在、地震保険や火災保険への加入を検討されている方、または既にご加入で追加・見直しを考えている方は、複数の保険会社をしっかりと比較検討し、最もお得なプランを選びましょう。まだ火災保険や地震保険に加入されていない方、あるいは現在加入している火災保険からの乗り換えを検討中の方は、以下のページから他社との比較が可能です。
フラット35Sと耐震等級3の組み合わせで「金利0.25%」引き下げ!(2025年2月現在)

耐震等級3の建物であれば、金利Aプランのフラット35Sを利用でき、フラット35の借入金利を当初10年間、0.25%引き下げることが可能です。(2025年2月現在)
例えば、借入金額が4000万円、借入期間が35年、適用金利が1.5%の場合、通常のフラット35では総返済額が51,438,985円になります。
一方、フラット35Sの金利Aプラン(0.25%引き下げ)を利用すると、総返済額は50,464,324円となり、通常のフラット35と比べて総返済額が974,661円も安くなります。さらに、耐震等級3にすることで、地震保険の割引で約448,000円安くなり、フラット35Sで970,000円安くなるため、合計で約1,420,000円も節約できることになります。
耐震性能の高い住宅に住むことで、安全性を高めるだけでなく、地震保険料の割引やフラット35の金利引き下げといった経済的メリットも享受できます。耐震等級3を取得することで、安心とお得の両方を手に入れましょう!
💡 今なら無料でプロに保険相談もできます。
▶︎【相談無料】保険のプロに「うちの場合どうすればいい?」を聞いてみる
🔗 次に読むおすすめ記事はこちら
「うちは戸建てだし、耐震性も高いから地震保険はいらないかも?」そんなふうに思ったことはありませんか?地震保険は任意の保険であり、住宅ローンのように必須ではありません。そのため、「入るか・入らないか」を自分で判断する必要があります。**あなたの家が地震保険に入るべきか?**を次の記事で一緒に考えていきましょう。
📌 詳しく知りたい方はこちらの記事へどうぞ
👉地震保険は戸建てにいらない?判断のポイントと後悔しない選び方
まとめ|耐震等級3で保険もローンもお得!安心の家づくりを
耐震等級3の住宅は、ただ“地震に強い”だけではありません。地震保険料の大幅割引(最大50%オフ)や、住宅ローン金利の優遇といった金銭的メリットも得られます。さらに、震度7の地震が繰り返し起こっても倒壊しにくいという、安全性の高さが大きな魅力です。

地震に強い家を建てることで、住宅コストを抑える方法について解説しました。一見、難しそうに思えるかもしれませんが、皆さんがやることはとても簡単です。**建築会社に「許容応力度計算で耐震等級3の家」を建ててください!**とお願いするだけで良いのです。
耐震等級3の家を建てることで、地震保険の「耐震等級割引」が適用され、フラット35Sの金利Aプランを利用すれば、住宅コストが大幅に削減できます。ただし、簡易的な計算で建てる建築会社もまだ多く存在するため注意が必要です。同じ耐震等級3でも、簡易計算では十分な耐震性能が確保できない場合があります。
「許容応力度計算」に基づいた安全性の高い設計を採用することで、家は大きな地震に耐え、地震後も軽い補修程度で住み続けることが可能になります。いつ大きな地震が発生するかは予測できませんが、しっかりと備えることで、大切なご家族の命や貴重な財産を守ることができます。
▶ 少しの初期投資が、将来の大きな安心に
「耐震等級3は高いのでは?」と思われる方も多いかもしれませんが、初期コストの差は、地震後の補修費用・住み替えリスク・保険料・金利差ですぐに回収可能です。つまり、**少しの追加費用で「安心を買う」**というのが、これからの住宅選びのスタンダードと言えるでしょう。
▶ 今すぐできること:まずはプロに相談を!
耐震等級3に対応した住宅を建てるには、信頼できる工務店・ハウスメーカー選びが鍵となります。最近では「標準仕様で耐震等級3対応」の会社も増えており、コストを抑えて高性能な家づくりが可能です。
✅ 資料請求や無料相談だけでもOK!
まずは気軽に専門家に話を聞いてみることで、不安や疑問を解消できます。
📩 家づくり、何から始めたらいいか分からない方へ
建築費の相場や住宅会社の特徴を知るには、比較資料の取り寄せが最初の一歩。以下のサービスを活用すれば、あなたの条件に合った住宅会社の提案を一括で取り寄せ可能です。
➡️ 家を建てるにはまず何から始めるべき?初心者向けの4つの手順と具体的な流れを解説!
✅ 家づくりやお金のことをもっと詳しく知りたい方はこちら
- 👉 耐震等級3とは?本当に必要?等級1・2との違いと後悔しない選び方
「地震保険が必要か迷う前に、まずは家の耐震性をチェックしておきたい」という方は、こちらの記事もぜひご覧ください! - 👉自宅駐車場を貸して稼ぐ!『akippa』 vs 『特P』完全比較で最適な選択法
空き駐車場があれば誰でも簡単に駐車場経営ができる、駐車場シェアリングサービスは御存じでしょうか?この記事ではまだまだ普及率の低い駐車場シェアリングサービスを、我が家で使っている実体験をもとに解説します。 - 👉【2025年最新】タウンライフ家づくりの評判まとめ|使って分かったメリット・注意点
タウンライフなら複数社の見積りを比較できるから適正価格が分かります。間取りや土地の提案がもらうことができるので、家づくりが一気に進みます。
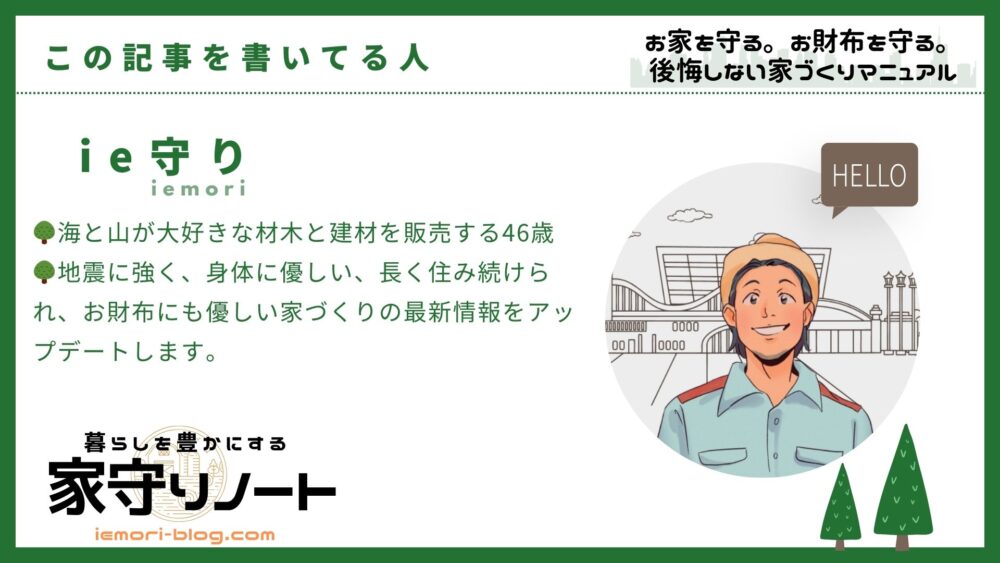
この記事に関して質問や相談、リクエストなどあればお問い合わせいただくか、(X)Twitterで DMください。お待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございました。
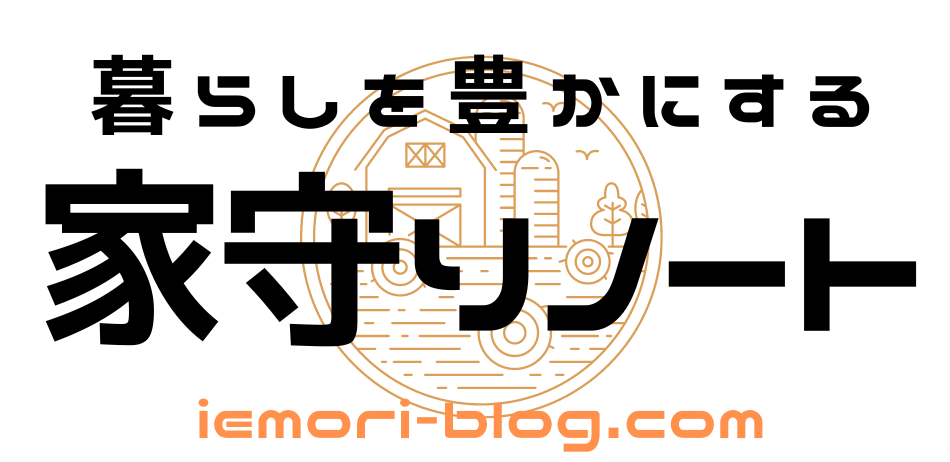
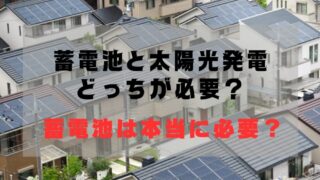
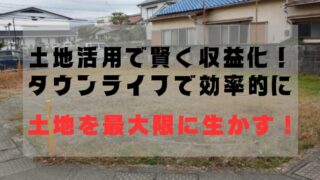
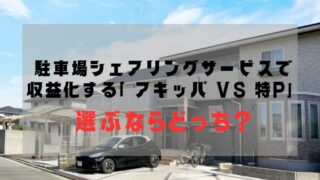
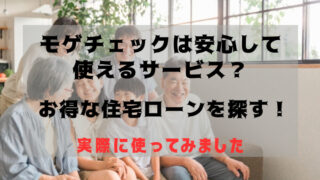

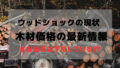

コメント