近年、日本各地で大規模地震が頻発し、家づくりの常識が変わりつつあります。2016年の熊本地震では、「耐震等級2」の建物ですら倒壊する事例が報告され、最高ランクの**「耐震等級3」**の住宅が、ほとんど被害を免れたという事実が明らかになりました。「耐震等級1」や「長期優良住宅レベルの等級2」では、震度7が連続する地震(繰り返しの余震)に耐えられないリスクがあります。これからの家づくりで最優先すべきは、内装や設備よりも「家族と財産を守る、最高レベルの耐震性」です。
そんなあなたの疑問にお答えするために、私は長年、地震に強い工法や建材を数多く見てきた経験から、多くの工務店とお施主様から高く評価されている**「耐震性能を大幅に高めるコーチパネル」**をご紹介します。この記事を読み、建物の仕様に取り入れることで、あなたは**「地震が起きても避難する必要がない、自宅が家族にとって一番安全な場所」**という安心感を手に入れることができます。
耐震性能を更に高めるコーチパネルで地震に備える!
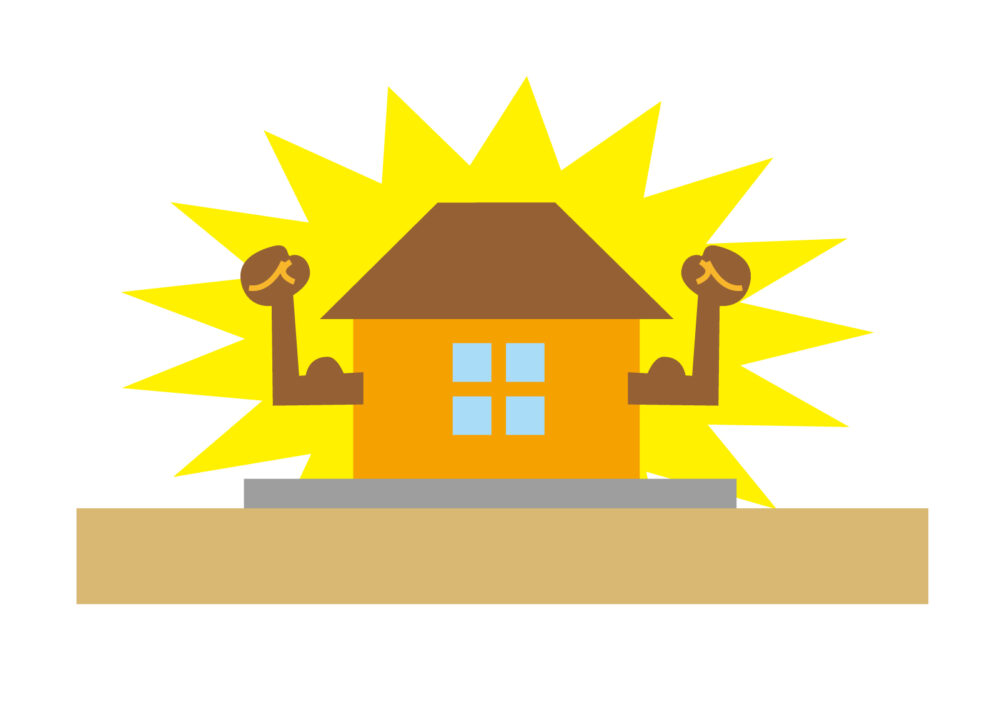
こちらの構造編では、仕様規定(壁量計算)の簡易的な計算ではなく、(構造計算)の建物の安全性を確認するための計算による「許容応力度計算で耐震等級3」の構造に設計することをオススメしています。同じ耐震等級3でも、詳細な計算による耐震等級3で設計するほうが耐震性能は上がります。耐震等級3は防災の拠点となる消防署や警察署などと同じ耐震性になる最強の構造です。
👉耐震等級3の家は地震保険が半額に!住宅ローンも優遇されるって本当?
耐震等級3の地震に強い家にすることで、地震保険の「耐震等級割引」を使うことができます。火災保険や地震保険の加入がまだの方、火災保険の見直しをして乗り換えを検討中の方はこちらの記事をご覧ください。
木造で最強の構造にする!高耐震パネルのコーチパネルとは?

まずはこちらの動画をご覧ください。
こちらの動画では、「片筋違い工法」、「大壁直貼り工法」、「コーチパネル」の3つの工法に同じ揺れを与えて破壊実験をしています。この3つの工法の中でコーチパネルが大きな揺れに何度も耐えています。同じ耐震等級3にする場合でも「片筋違い」、「大壁直貼り」、「コーチパネル」では工法によって実際の耐震性が大きく変わるのが分かります。「片筋違い」や「大壁直貼り」は節や割れなどの材料による精度や、釘を打つ場所や圧力など大工さんの施工精度の違いによっても耐震性が変わります。
その点「コーチパネル」の場合は工場生産で、釘を打つ場所や圧力が一定になるので、パネルの製品精度を安定させることができます。大切な家族の命を守るような大事なところは、人間の技能や技術に左右されない、製品精度が安定している「コーチパネル」採用したいですね。
「片筋違い」と「大壁直貼り」工法のメリットとデメリット
この「片筋違い」と「大壁直貼り」の工法は一般的な工法で、多くの工務店やハウスメーカーで取り入れている工法です。「片筋違い」の場合、木材の節の位置や大きさ、木材の割れや施工精度によって強さのバラつきが出てしまいます。「片筋違い」工法のメリットはコスト面です。バランスよく配置することで、コストを掛けずに耐震等級3を取ることが可能です。


「大壁直貼り」の場合、地震の力を耐力面材の面全体に力を分散させますので、建物の倒壊を防ぎます。ただし、釘打ちの精度によって強さが変わる欠点もあります。この「大壁直貼り」の欠点は地震が起きた場合、面材は強いのですが面材を留めている釘が地震の大きな揺れによって外れてしまいます。
高耐震パネルのコーチパネルは地震に強い!

コーチパネルの強さを数字に表すと、壁倍率は、4.8相当になります。 従来の工法「片筋違い」や「大壁直貼り」に比べて、約2倍の耐力と、約1.6倍もの粘り強さを発揮します。これが実際どれくらいの揺れに耐えられる強さかというと、 震度7強を超える巨大地震や、繰り返し来る余震にも耐えられる程の強さです。
コーチパネルは強さ以外のメリットもたくさん!
このコーチパネルは地震に強いところが一番のメリットですが、強さ以外でもメリットがたくさんあります。
①枠材と耐力面材と断熱材が一体になっているので施工が早い。
②釘を打つ圧力と打つ箇所の組み立て精度が安定している。
③上棟時に施工するので壁断熱までの施工が早い。
④上棟翌日にはサッシの施工ができる。
⑤雨で建物内部が濡れる心配がなくなる。
⑥上棟後すぐに防犯対策になる。
⑦隙間のない断熱施工ができ、気密を取りやすい。
⑧上棟日に耐力面材と断熱材までの施工が終わるので工期が短縮できる。
⑨約2週間の工期短縮ができるので大工の施工手間が減る。
⑩電気配線をしやすい。
⑪高断熱施工もできる。
⑫室内側からパネルをはめるので安定した足場での施工ができる。
⑬壁紙クロスの浮きや剥がれが激減します。
⑭工期短縮につながるので、近年の職人不足に有効。
間柱の枠材に耐力面材と断熱材が組まれて一体のパネルになっていることで、施工が格段に速くなります。コーチパネルは、上棟日の大工さんがたくさんいる時に施行しますので、上棟1日目で耐力面材と壁断熱の施行が終わります。圧倒的な速さで工期を短縮することができます。引渡し後に壁のクロスが浮いたり剥がれたりすることが良くありますが、構造がガッチリ固まることでクロスが動かなくなるので浮いたり剥がれたりすることが激減されます。

コーチパネルの商品代が入りますので建物の費用が上がるように見えてしまいがちですが、約2週間の工期短縮ができたり施工手間が大幅に減りますので、総合計のコストで見るとそこまで大きな額のコストアップにはなりません。工務店にとってもお施主さんにとってもメリットがいっぱいですね!
コーチパネルを施工すると、窓の位置が正確に決まるため、上棟の翌日にはサッシの取り付けが可能になります。これにより、防犯性が高まるだけでなく、建物内部が雨で濡れる心配もなくなります。
床合板や屋根合板、さらにハウスメーカーで多く採用されている集成材の梁・桁・柱などは、いずれも接着剤(糊)で貼り合わせて作られています。そのため、雨に濡らさない施工が非常に重要です。
特に合板は水分を吸うと剥離しやすく、床鳴りの原因になったり、カビが発生する恐れがあります。最近の住宅は高気密・高断熱化が進んでいるため、もしカビが発生しても乾燥しにくく、壁の中でカビが繁殖してしまうリスクが高まります。
コーチパネルのデメリットを理解する!
コーチパネルには多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。そのため、メリットだけでなくデメリットも理解したうえで検討することが大切です。
デメリットの一つとして、断熱材の選択肢が限られている点が挙げられます。使用できる断熱材は基本的にネオマフォームとスタイロフォームの2種類に限定されています。

防火構造認定に対応することは可能ですが、コーチパネルの場合は内部からパネルをはめ込む工法のため、外壁側の柱が見える形で面材が張られます。そのため、たとえ防火性能を有する面材を使用していても、柱が露出している状態では防火構造認定を取得できません。
防火構造認定を取得するには、外壁の下地としてプラスターボードを追加で施工する必要があります。この工程が増える分、手間とコストがかかる点がデメリットです。
ただし、窯業系サイディングを使用する場合は、プラスターボードによる外壁下地を省略できるケースもあります。
まとめ:木造住宅の工法選びと耐震性能の重要性

木造住宅を建てる際は、採用する工法によって耐震性能が大きく変わります。「片筋違い工法」「大壁直貼り工法」「コーチパネル工法」の3つを比較した破壊試験の映像からも、その性能差は明確に示されています。
中でもコーチパネル工法は、コストがやや高くなるというデメリットはあるものの、優れた耐震性によって地震に強い家づくりを実現できる点が最大の魅力です。
さらに、工期の短縮や施工精度の安定性に加え、雨仕舞いや防犯面での安心感も高く評価されています。
家の構造は、一度建ててしまうと簡単に変更することはできません。そのため、後から交換できるキッチンやお風呂などの設備グレードを少し抑えてでも、耐震性能の高い構造を選ぶことが、家族の安心と安全を守るうえで最も重要と言えるでしょう。

地震に強い家を建てることは、将来の安全と安心を確保する上で大切な選択です。
つづきは下の記事へ
👉【木造で最強の構造!】地震に強い家にして保険料と住宅ローンを安くする方法!
耐震等級3の構造(骨組み)を金物工法で組み、コーチパネルを組み合わせることで、地震が起きても避難の必要がない最強の家づくりについて詳しく説明しています。木造住宅でコストを抑えつつ、地震に強い最強の家を目指す方は、ぜひご覧ください。必見の内容です!

建ててから後悔しないように地震に強い最強の家を目指しましょう!
次に読むと役立つ関連記事
- 【要注意】火災保険の一括見積もりサービスに潜む3つのデメリットとは?
これから火災保険を見直したい方や新規加入を検討している方はご覧ください。 - タウンライフ家づくりを使って分かったメリット・注意点はこちらです。
タウンライフなら複数社の見積りを比較できるから適正価格が分かります。間取りや土地の提案がもらうことができるので、家づくりが一気に進みます。 - 自宅駐車場を貸して稼ぐ!『akippa』 vs 『特P』完全比較で最適な選択法
まだまだ普及率の低い駐車場シェアリングサービスを、我が家で使っている実体験をもとに解説します。 - 災害用ポータブル電源のおすすめ完全ガイド|容量・使い方・選び方のポイント
災害時に必要な容量の目安・正しい使い方・失敗しない選び方・おすすめモデルをわかりやすく解説します。
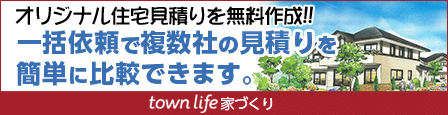
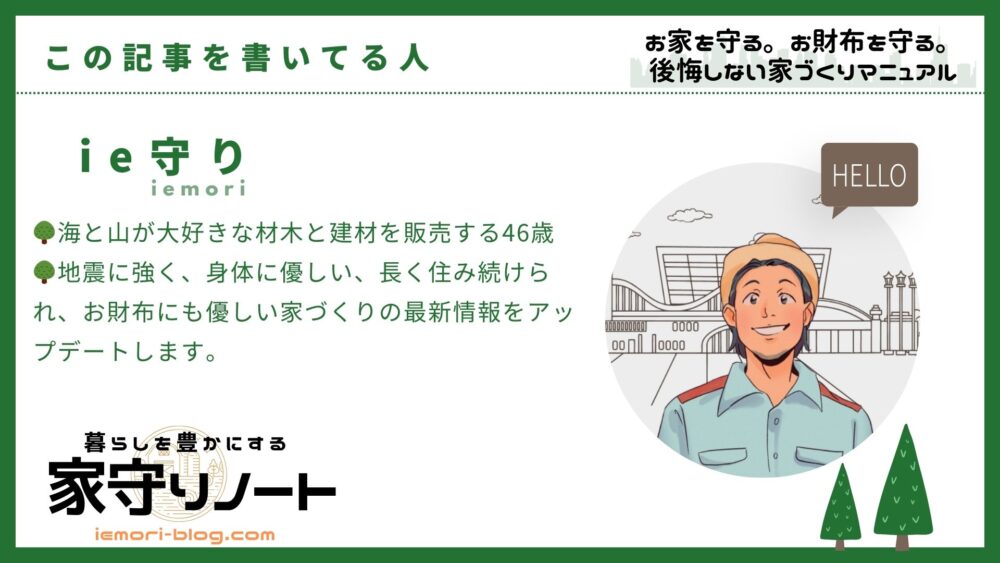
この記事に関して質問や相談、リクエストなどあればお問い合わせいただくか、(X)Twitterで DMください。お待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございました。
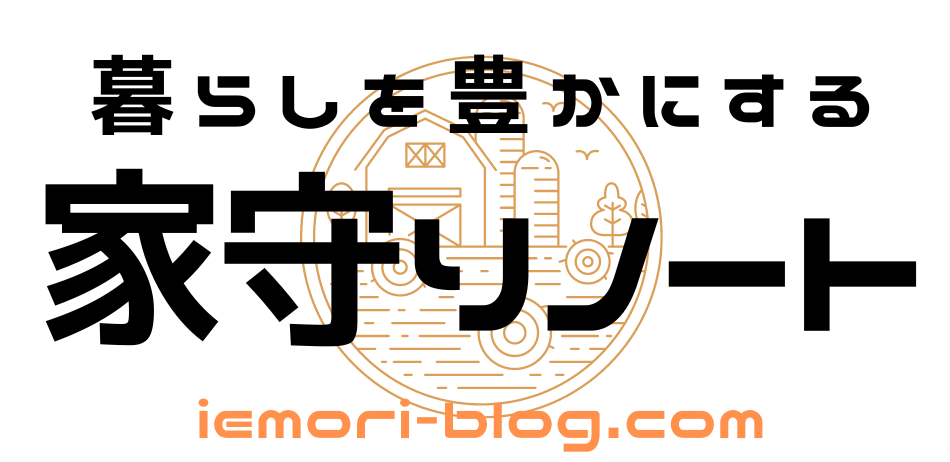
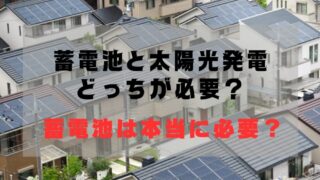
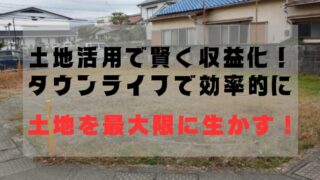
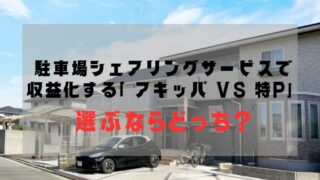
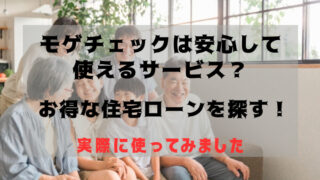
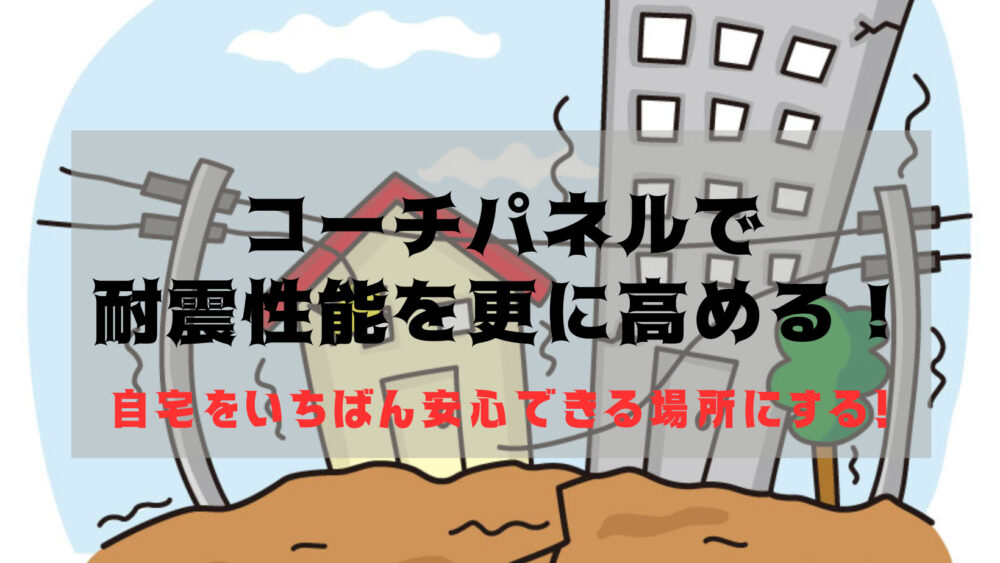


コメント