「相続した実家が空き家のまま放置されている」「中古住宅を購入してリノベしたいけど、費用がいくらかかるか不安」──そんな悩みを持つ方は少なくありません。実際、空き家リノベーションは新築よりも費用を抑えられる可能性がある一方で、思わぬ追加工事や構造補強が必要になるケースもあります。また、2026年現在は国や自治体の補助金制度が充実しており、上手に活用すれば数百万円のコスト削減も可能です。
本記事では、空き家リノベーションにかかる費用の相場から、最新の補助金制度の活用方法、注意すべきポイントまでわかりやすく解説します。「空き家を再生して快適に暮らしたい」「補助金を活用してお得にリノベしたい」という方はぜひ最後までご覧ください。

空き家リノベーションの費用相場【2026年最新版】

空き家をリノベーションする際に最も気になるのが「費用はどのくらいかかるのか」という点です。費用感を理解せずに計画を進めると、予算オーバーや追加工事で思わぬ出費につながりかねません。ここでは、リフォームとの違いを確認したうえで、空き家リノベーションにかかる費用相場を詳しく解説します。
リノベーションとリフォームの違い

まず整理しておきたいのが「リフォーム」と「リノベーション」の違いです。
- リフォーム:老朽化や劣化した部分を修繕し、建物を「元の状態に戻す」工事。壁紙の張り替えや水回り設備の交換などが該当します。
- リノベーション:間取り変更や断熱性能の向上など、大規模な改修を行い「新たな価値を加える」工事。デザインや機能性を向上させるのが目的です。
空き家を快適に暮らせる住宅へ再生するには、多くの場合リノベーションが必要となり、工事規模も大きくなるため費用相場もリフォームより高めになります。
空き家リノベーションにかかる費用の目安
空き家のリノベーション費用は、建物の状態や工事内容によって大きく変動します。2026年時点での一般的な目安は以下の通りです。
- 部分的な改修(内装・水回りなど):100万〜500万円
- 主要な設備更新+間取り変更を伴う改修:500万〜1,000万円
- フルリノベーション(スケルトンにして全面改修):1,000万〜2,000万円以上
特に空き家は劣化が進んでいるケースが多く、耐震補強や断熱改修などを含めると費用はさらに増える可能性があります。
部分リノベとフルリノベの費用比較

空き家リノベーションには「部分リノベ」と「フルリノベ」があります。
- 部分リノベーション
- 費用:100万円〜800万円
- 範囲:キッチン・浴室・外壁など一部のみ改修
- メリット:コストを抑えやすい
- デメリット:建物全体の価値向上には限界がある
- フルリノベーション
- 費用:1,000万円〜2,500万円
- 範囲:間取り変更、耐震補強、断熱工事を含む全面改修
- メリット:資産価値の向上、長期的に安心して住める
- デメリット:初期費用が高い
空き家を「売却したい」「賃貸に出したい」と考える場合は、フルリノベーションの方が投資対効果を得やすいのが特徴です。
費用が高くなるケース・追加工事の注意点
空き家リノベーションでは、想定外の工事費用が発生することも少なくありません。特に注意したいのは以下のポイントです。
- 基礎の劣化やシロアリ被害 → 補修費用100万円〜300万円
- 給排水管や電気配線の老朽化 → 交換費用50万円〜200万円
- 断熱材の入れ替えや耐震補強 → 数百万円単位の追加工事
古い空き家ほど、現地調査をしっかり行わないと、契約後に「予算オーバー」になりがちです。
そのため、複数の業者から相見積もりを取ること、補助金や助成金の活用を事前に確認することが重要です。
空き家リノベーションの補助金制度を徹底解説
空き家リノベで「補助金を使えるかどうか」は、実際の負担額を大きく左右します。2026年現在、国の大枠制度に加え、多くの自治体が独自の助成や加算を用意しているため、「国+自治体」の組み合わせで数十万〜数百万円規模の支援を受けられることが多いです。まずは国の代表的な制度と、自治体でよくある補助のタイプを押さえましょう。
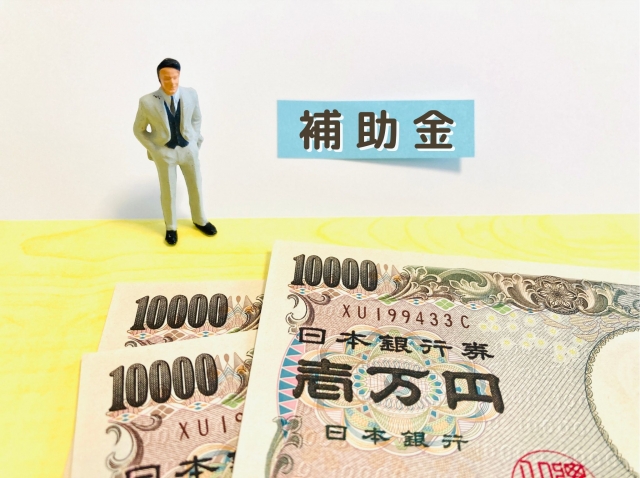
国が実施する主な補助金制度|みらいエコ住宅2026事業とは?
国が実施する住宅向け補助金制度の中でも、2026年版の代表的な制度が「みらいエコ住宅2026事業」です。
この制度は、住宅の省エネ性能向上・耐震性強化・断熱改修・バリアフリー化・給湯省エネなどの工事を支援する国の補助金制度です。新築住宅や既存住宅リフォームの性能向上を後押しし、2026年の住宅リフォーム・新築支援の中心となります。
🔧 既存住宅(リフォーム)向け補助金
みらいエコ住宅2026事業は既存住宅のリフォームにも対応し、省エネ改修・断熱化・バリアフリー・設備更新などの工事を補助します。
リフォームの補助金額(1戸あたり上限)
- 省エネ改修(断熱・設備更新など)
👉 最大100万円 - 高断熱窓の設置
👉 最大100万円 - 高効率給湯器の設置(エコキュート/ハイブリッド給湯機/エネファーム)
👉 最大17万円

工事内容の組み合わせや住宅条件により補助額は変動します。
📌 みらいエコ住宅2026事業の活用メリット
✔ 高額補助で初期費用を大きく軽減
GX志向型住宅では最大110万円の補助が受けられるため、高性能住宅へのハードルを大きく下げられます。
✔ 新築・リフォームの両方に対応
これから家を建てる人だけでなく、既存住宅の断熱・省エネリフォームを検討している人にも使える制度です。
✔ 光熱費削減+住宅価値アップ
省エネ性能の向上により、
- 光熱費の削減
- 住まいの快適性向上
- 将来的な資産価値の維持
といったメリットも期待できます。
みらいエコ住宅2026事業を使う際の注意点
- 着工前の申請が原則必須
- 補助対象となる工事・住宅性能が細かく定められている
- 予算上限に達すると受付終了
特に2026年は申請集中が予想されるため、早めの情報収集と事前準備が重要です。
※令和7年11月28日以降の着工現場が対象になります。
👉みらいエコ住宅2026事業の概要資料はこちら
自治体ごとの補助金・助成金の種類と条件
自治体(都道府県・市区町村)は地域政策に合わせて様々な支援を打ち出しています。代表的な例としては以下のようなタイプがあります。
- 空き家購入+改修支援:物件購入と改修をセットで補助(例:移住者向けに上限数十万〜数百万円まで支給される自治体あり)。
- 解体補助:空き家を解体する場合に解体費の一部を補助(補助率1/2〜2/3、上限数十万〜150万円程度の事例あり)。
- リノベ補助(改修費用の一部):改修費の1/3〜2/3、上限は自治体で幅があり、数十万円〜150万円以上のケースもある。
実務上の注意点
- 自治体ごとに対象工事や対象者(移住者、空き家所有者、賃貸転用等)の条件が異なるため、申請前に自治体の窓口や公式サイトで最新条件を必ず確認してください。
補助金を利用する際の流れと申請のコツ
一般的な申請の流れ(スムーズに進めるための実務手順)
- 事前相談:自治体の空き家担当窓口や相談窓口へ相談し、制度の対象か確認。
- 物件調査(インスペクション):建物の劣化具合、構造、安全性をチェック(国の制度ではインスペクション費用が補助対象になることも)。
- 事業計画(見積・設計)作成:補助要件に合う工事内容を設計し、見積りを取得。
- 申請書類の提出:自治体所定の書類を用意して申請(添付資料/見積書/所有者同意書など)。
- 交付決定 → 工事 → 完了報告:交付決定後に工事を実施し、完了報告を提出して補助金交付。
申請のコツ(採択率・交付額を上げる)
- 要件に沿った計画書を丁寧に作る(目的・効果を明確に)。国や自治体は「地域貢献性」「省エネ性」「住み替え促進」等を重視する場合が多い。
- 複数の補助制度を組み合わせられないか確認する(国+自治体で併用できる事例あり)。ただし重複支援の規定があるため、事前確認が必須。
- 期限や交付枠に注意:年度ごとに予算枠があるため、早めに相談・申請する。
補助金を使うといくら費用が削減できる?
補助額は制度・自治体・工事内容で大きく異なりますが、**目安としては「数十万円〜数百万円」**の削減が期待できます。具体例を示すと
- 国の長期優良住宅化リフォームでの支援や、省エネ・耐震等の要件を満たすことで数十万〜100万円程度の支援が得られるケースがあります(制度により上限や要件が変わります)。
- 自治体独自の空き家活用支援を組み合わせると、合計で100万円以上の支援が受けられる事例も報告されています(移住者向け購入+改修支援など)
- 解体補助だけでも上限50万〜150万円程度が出る自治体があり、解体→建替えやリノベ計画の初期費用を大幅に下げられる場合があります。
※重要:上の金額はあくまで事例とガイドラインに基づく目安です。実際の交付額は申請条件・補助率・上限額・予算枠によって変わります。必ず「自治体の公式情報」や「国の公式ページ」を確認してください。
最後に — 補助金で賢く空き家リノベを進めるためのチェックリスト
- まずは自治体窓口へ事前相談(制度の適用可否が短時間で分かる場合あり)。
- インスペクションを早めに実施して必要工事を洗い出し、補助金要件を満たす設計にする。
- 国の制度と自治体制度の併用可否を確認(場合によっては合算で大きな支援が得られる)。
- 申請書は目的(地域貢献・省エネ・耐震等)を明確に。採択されやすくなるポイントです。
空き家リノベーションの成功事例と失敗事例

空き家リノベーションを検討している人にとって、実際にどんな事例があるのかはとても気になるポイントです。成功事例からは「コストを抑える工夫」や「補助金の活用方法」を学べ、失敗事例からは「後悔しないための注意点」を知ることができます。ここでは、具体的なケースをもとに解説します。
費用を抑えて快適に暮らせるようになった事例
築40年の木造空き家をリノベーションしたAさん(東京都郊外)のケースです。
- Before:雨漏りや水回りの劣化が進み、居住は難しい状態
- 工事内容:屋根・外壁の補修、断熱材の入れ替え、水回り設備を一新
- 費用:800万円
【成功のポイント】
- 「フルリノベ」ではなく 部分リノベーションを選択し、居住に必要な部分だけを重点的に改修した
- 断熱材やサッシを更新したことで、冬は暖かく夏は涼しい住まいに改善
- 工事後の光熱費が年間5万円ほど下がり、ランニングコスト削減にも成功

👉 空き家リノベでは「必要な部分だけを改修する」ことで、費用を抑えつつ快適性をアップさせることができます。
補助金を活用してコスト削減に成功した事例
地方都市で空き家を購入し、移住したBさん夫婦のケースです。
- Before:築35年、耐震性に不安がある中古空き家
- 工事内容:耐震補強、キッチン・浴室の水回りリノベーション、バリアフリー工事
- 費用:1,200万円
- 補助金活用:国の「長期優良住宅化リフォーム推進事業」で最大120万円、自治体の移住支援補助金で150万円を受給
【成功のポイント】
- 早い段階で自治体窓口に相談し、補助金の条件を確認
- 耐震補強やバリアフリーといった「補助対象工事」を組み合わせて計画
- 合計270万円の補助を受けられ、自己負担を約1,000万円まで圧縮

👉 空き家リノベを計画するときは、補助金を組み合わせることで数百万円単位の削減が可能です。
失敗しやすいポイントと後悔を防ぐ方法
一方で、空き家リノベーションには失敗事例も少なくありません。よくあるケースは以下の通りです。
- 追加工事で予算オーバー
→ 解体してみたらシロアリ被害や配管劣化が見つかり、見積もりより+200万円かかった。
→ 対策:事前に**インスペクション(建物診断)**を行う。 - 補助金が使えなかった
→ 工事を始めてから補助金の存在を知ったが、着工前申請が条件で利用できなかった。
→ 対策:必ず着工前に補助金制度を確認・申請する。 - 生活動線が合わなかった
→ 住んでから「収納が足りない」「子育てに向かない間取り」と後悔。
→ 対策:設計段階でライフスタイルや将来の暮らしをイメージして計画する。

👉 失敗を防ぐには、事前調査・補助金申請・生活動線の確認が必須です。
成功事例に学び、失敗を防ぐリノベ計画を
- 成功事例から学べること:
→ 部分リノベで費用を抑える/補助金を組み合わせて大幅削減 - 失敗事例から学べること:
→ 追加工事リスク・補助金申請のタイミング・間取り設計の甘さ
空き家リノベーションは「工事費+補助金活用+生活設計」をしっかり組み合わせることで、失敗を防ぎ、資産価値を高める住まいづくりにつながります。
空き家リノベーションを失敗しないための進め方チェックリスト
空き家リノベーションは「何から始めればいいかわからない」という方が多いのが現実です。そこで、後悔しないために最低限押さえておきたい進め方をチェックリスト形式でまとめました。

1. 物件の現状調査をしっかり行う
- シロアリ被害や雨漏りなど「隠れた劣化」がないかを確認する
- 耐震基準に合っているか、補強が必要かを専門家に診断してもらう
- 断熱・配管・電気系統など、生活に直結する部分も要チェック

👉 調査結果を軽視して工事を進めると、追加費用で予算オーバーになるケースが多発しています。
2. リノベーションの優先順位を決める
- 「住める状態にする」最低限の工事なのか
- 「快適さ・デザイン性」を重視するのか
- 「資産価値を上げる」投資目的なのか
👉目的を明確にすることで、予算配分と工事内容がブレにくくなります。
3. 補助金・減税制度を活用する
- 耐震改修や省エネリフォームは補助金対象になることが多い
- 長期優良住宅リフォームを視野に入れると減税も受けられる
- 申請期限や必要書類を早めに確認しておく

👉 補助金をうまく使えば、数十万~数百万円のコスト削減につながります。
4. 信頼できる業者を複数比較する
- 相見積もりは最低3社
- 見積もり内訳に「一式」とだけ書かれていないか確認
- 実績や口コミだけでなく、担当者の対応力も重要
👉 リノベーションの失敗は「業者選びの失敗」に直結します。
5. 工事後の維持・メンテナンス計画を立てる
- 外壁や屋根は10~15年ごとに点検が必要
- 水回り設備は20年を目安に交換を検討
- 定期点検をお願いできる業者と付き合っておく
✅ チェックリストまとめ
この流れを踏むことで「やるべきことが抜け落ちる」リスクを防げます。空き家リノベーションは一度始めると後戻りが難しいため、計画段階でこのチェックリストを参考に進めるのが安心です。
👉優良工務店を見分ける6つのポイントを解説!【後悔しない家づくり】
自分たち家族のライフスタイルに合った注文住宅を楽しみながら建て、建てた後も安心してメンテナンスを任せられる優良工務店の見分け方を解説します。
まとめ|補助金を活用してお得に空き家リノベーションを成功させよう
費用相場を把握して計画的に進める
空き家リノベーションを成功させる第一歩は、まず費用相場を正しく把握することです。
部分リノベなら数百万円、フルリノベでは1,000万円を超えるケースもあり、予算感を間違えると計画が頓挫してしまいます。最初の段階で「どこにいくらかかるのか」を整理し、優先順位をつけて工事内容を決めることが大切です。
国・自治体の補助金を活用して数百万円の節約も可能
近年は空き家活用を後押しするために、国や自治体による補助金制度 が充実しています。
例えば「長期優良住宅化リフォーム推進事業」や「子育て世帯向けの空き家活用補助」などを利用すれば、数十万円から数百万円の負担軽減も可能です。地域によっては耐震改修やバリアフリー化に特化した助成金もあるため、必ず情報をチェックしましょう。
補助金を上手に組み合わせることで、予算オーバーを防ぎつつ理想のリノベーションを実現できます。
信頼できる業者選びが成功のカギ

費用や補助金をうまく活用できても、業者選びを誤るとリノベは失敗しやすいのが実情です。
複数社に見積もりを依頼して比較するのはもちろん、過去の施工実績や補助金申請のサポート体制もチェックポイント。特に空き家リノベは「追加工事が発生しやすい」ため、見積り段階でリスクを丁寧に説明してくれる会社を選ぶことが安心につながります。
💡 まとめると
- 相場を理解して無理のない計画を立てる
- 国・自治体の補助金を積極的に活用する
- 信頼できる業者と二人三脚で進める
これらを意識すれば、空き家リノベーションは費用を抑えながら安心して成功させることができます。
👉無料で貰えるお見積り提案でリフォーム会社を比較できます。一括見積もりサービスなら、信頼できるリノベーション会社を無料で探せるので安心です。
次に読むと役立つ関連記事
- 古民家リノベの費用と注意点|自然素材を活かす再生のコツと成功事例
古民家リノベーションの費用や注意点、自然素材を活かすコツをわかりやすく解説!補助金や成功事例も紹介し、後悔しない理想の古民家再生を実現します。 - 初めての外壁塗装!塗り替え費用や業者選びで失敗しないための基礎知識
外壁塗装が初めてでも安心して進められるように、外壁塗装の費用相場や業者選びの注意点、基礎知識を徹底解説しています。 - 自宅駐車場を貸して稼ぐ!『akippa』 vs 『特P』完全比較で最適な選択法
まだまだ普及率の低い駐車場シェアリングサービスを、我が家で使っている実体験をもとに解説します。

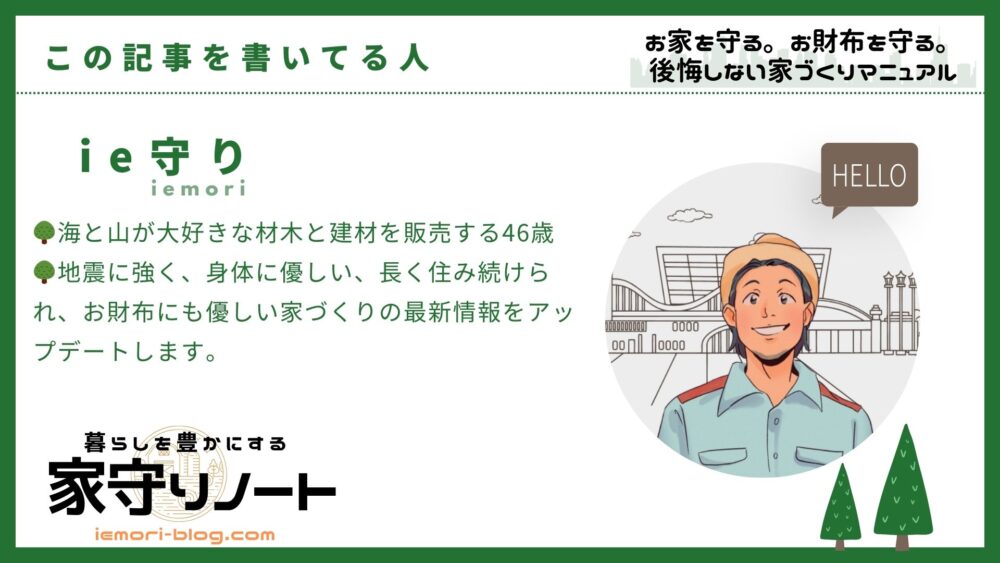
この記事に関して質問や相談、リクエストなどあればお問い合わせいただくか、(X)Twitterで DMください。お待ちしております。最後まで読んでいただきありがとうございました。
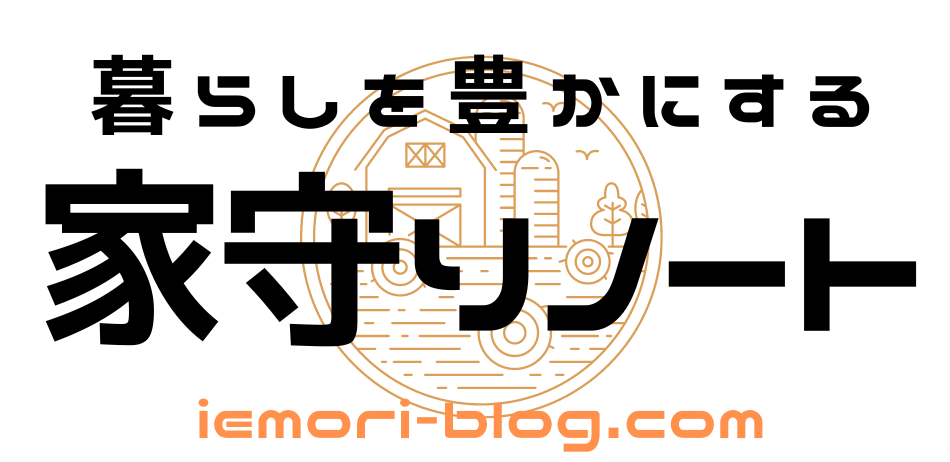
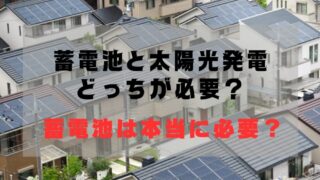
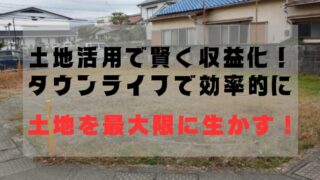
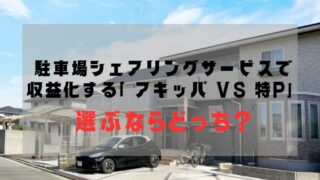
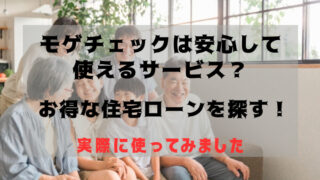
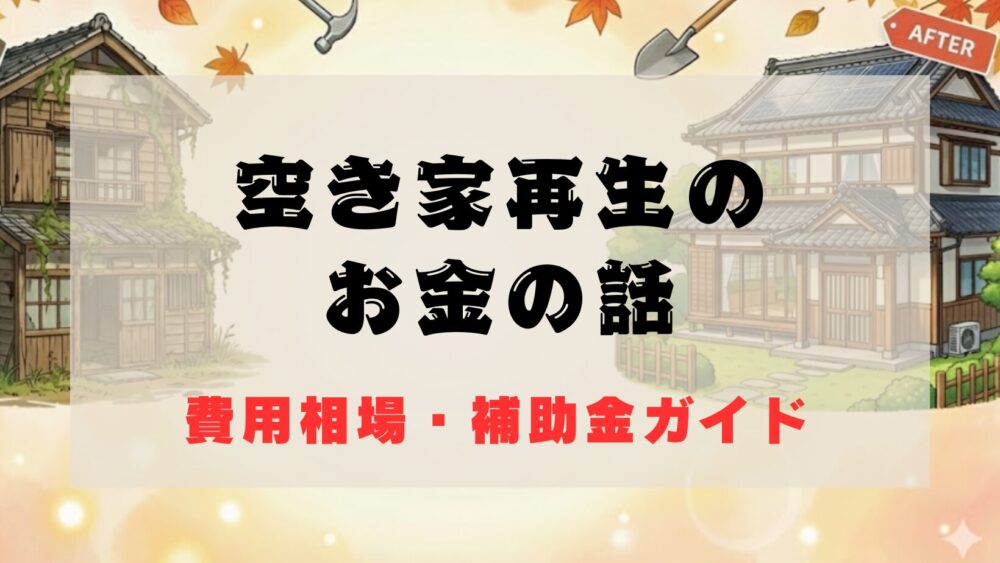

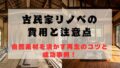
コメント